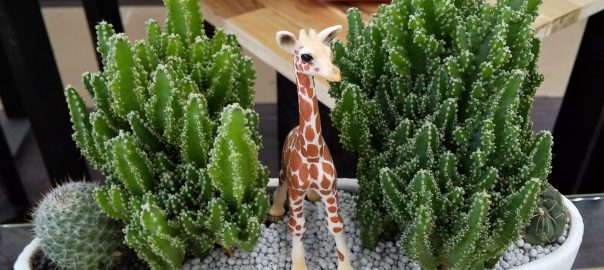マックス・リュティ『昔話の本質』報告
第8章謎かけ姫ー策略、諧謔、才智 つづき
今度は、お姫さまが謎をかけるのではなく、お姫さまが解けないような謎を出したものと結婚するという話です。どんななぞでも解ける賢いお姫さまの話。
これはたくさん類話があってね、昨日更新した《外国の昔話》「なぞなぞの好きなお姫さま」もそうだし、グリム童話KHM22「謎」もそうです。
ATU851「謎を解けない姫」で調べてみてね。
で、リュティさんは本書でフランスのしゃれた類話を紹介しています。
こういうのです。
「王女が三日かかっても解けない謎を出したものを夫にする。ただし、王女が謎を解いたら、謎を出したものは命を失う」というお触れが出ます。
王女は赤い服、金の冠、額にはダイヤモンド、手に白い棒。
城の周りには犠牲者の骸骨がずらり。
ブルターニュにケルブリニックという若い貴族がいて、王女のなぞを解きに出かける。
母親は、行かせたくなかったのに、どうしても行くというものだから、強い毒の入った飲み物を息子に持たせる。
ほら~、毒入りだよん。(「なぞなぞの好きなお姫さま」の解説を見てね。こちら⇒)
ケルブリニックは、とちゅうでプチ・ジャンという抜け目のない兵士と道連れになる。
プチ・ジャンは毒に気が付き、飲み物を二人の馬の耳に注ぎ込む。
馬たちは倒れて死ぬ。
馬の肉をついばんだ4羽のカササギも毒に当たって死ぬ。
プチ・ジャンは、途中の村で、カササギの肉を入れたお菓子を8個作らせる。
それを持って旅を続け、森の16人の盗賊に晩飯に招待される。おれいにカササギ入りのお菓子を提供する。
盗賊たちはぶっ倒れる。
プチ・ジャンは、これを謎にするわけです。
「家を出たとき、私たちは四つでした。
四つのうち二つが死にました。
その二つから四つが死にました。
その四つから八つを作りました。
その八つから十六が死にました。
今はまた四つになって私たちはあなたのところに突きました。」
この謎を、ケルブリニックは、必死で覚えながらお城へ向かうのです。
かなり長くて笑いどころが満載。
リュティさんは、フランスの昔話は風刺の味を好み、ドイツのようにひたむきでなく、ロシヤのように原初的でもない。粋なところがあるかと思うと、ある種の写実的な表現もあると言います。興味深いですね~
それはさておき、この類話、たくさんあるけど、共通点があるそうです。
それは、謎が話の筋からできていること。
主人公は、解決の方法も知らないで出かけていくんですね。
すると、ひとりでに謎が出来上がる。
つまり、ストーリーを重んじる昔話は、謎さえもストーリーから生まれる。
なるほど。確かに、これは面白い。
はい、今日はここまで。
つぎは、昔話と謎の関係です。
ところで、前回の宿題の答え、分りましたか?
オーストリアの「賢いお百姓の娘」
1、いちばん太っているものは何か?
2、いちばん美しいものは何か?
3、いちばん豊かなものは何か?
おっとっと、答えは来週月曜日HP更新で紹介することにしよう。
おもしろいから再話したのよ。
***********
おはなし会の報告
9月1日(火)
幼稚園5歳児 2クラス合同
ろうそくぱっ
おはなし「かきねの戸」
ろうそくぱっ
人数が多かったので力技だったけど、よう笑ってくれました~
笑いは大事!
感染予防をしっかりしてのおはなし会です。
わが市ではまだ新規感染者が出ているので、ほんと、勇気が要ります。
でも、語りが子どもに必要と考えてくださってるのが、泣きたいほどうれしいヾ(≧▽≦*)o