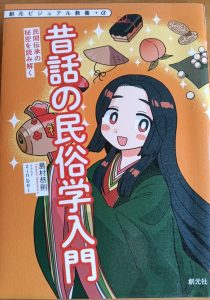遅くなりましたが、先週土曜日2月21日の図書館おはなし会の報告です。寒さが落ち着いたのはいいのですが、ひたひたと、迫りくる気配を感じますね~「わたし、カフンーさん、あなたのうしろにいるわ」~ あぁ、毎年ホントに嫌です。
さて、今回はヤンさんはお休み、担当はおらふの先輩です。三連休の初日のせいか、人気がまばらな図書館でしたが、常連さんの女の子が集まっておはなし会がはじまりました😊
子ども 6人 おとな 3人
手あそび うめにうぐいす
おはなし「だんだん飲み」『日本の昔話5』おざわとしお/福音館書店
絵本 『みて みて!』谷川俊太郎 ことば/小西貴士 写真/福音館書店
絵本 『にたものどうし』奥井一満 文/U.G.サトー 絵/福音館書店
手あそび キャベツのなかから
手あそび さよならあんころもち
かえるから始まって、しまいには鬼を飲み込んでしまうのですから、わぁ大変!と思うのですが、それで子どもは満足するんですね😄
図書館でヤンさんのする手遊び「ちいさなはたけ」を、わたしもお借りして幼稚園の子どもたちにするのですが、「ちいさなはたけ」から始まって、「ちゅうくらい」を済ませると、心得たとばかりに「おおきいはたけ」になり、そして「もっと大きいの!」と要求されます。それで「ばかでかいはたけ」。最後の「ドカーン」ではみんな決まってピョーンと跳ね上がります。ほんと上手くできてるなーと思いながらいながらやっているのですが、この「だんだん飲み」は、子どもにそんな満足感を与えてくれるのかなと思いながら聞いていました。最後には豆を投げて鬼も退治できますしね😊
続く絵本は写真の絵本と、写真のような絵の絵本で、少人数にはピッタリの細かさ。寄り合って絵本にがぶりつく姿はまさに「地域の文庫のおばちゃんと子どもたち」、という感じでした😊 おらふは残り数分のところで退席してしまったのですが、子どもたちからのリクエストがあって「キャベツのなかから」をしたりと、人数は少なかったけど盛り上がって楽しんでくれて良かったとのことでした😊