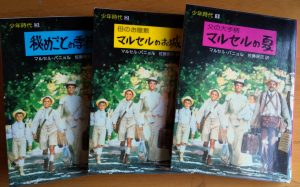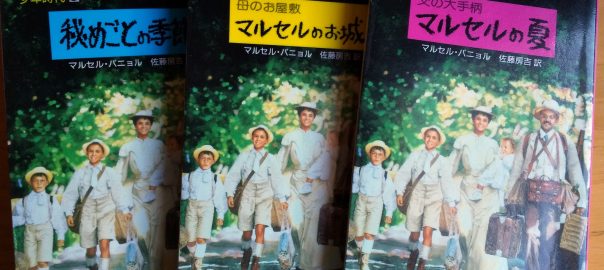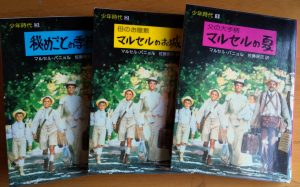『瀬田貞二子どもの本評論集児童文学論上』報告
お久しぶりです(笑)
マルセル・パニョルの自伝『少年時代』を読みました。
今から100年近く昔のフランス。町の様子や田舎の様子、自然にあふれた山の様子。まざまざと思い描きながら、みずみずしい感受性に、ワクワクしながら、読みました。
*********
第3章書評など
「少年時代」三部作 1976年
マルセル・パニョル(1895-1974)
フランスの劇作家。
最初に戯曲を書いたのは15歳のとき。
33歳で「トパーズ」が上演され、そののち、「マリウス」「ファニー」「セザール」の三部作で世界的な名声を得る。
その後、映画の製作も多く、51歳でアカデミー・フランセーズの会員になる。
『少年時代』が書かれたのは、60代になってから。1957~59年。
この書評が書かれたころの、日本の児童文学の世界では、子どもから大人への移行期の子どもたちに向けて書かれた文学がない時代でした。
瀬田先生は、第二次世界大戦後、世界では、中高生図書の意義が再検討され、この時期の子どもに向けた本を「橋」ととらえるようになったと書いています。
そして、このマルセル・パニョルの『少年時代』には、「橋」の資格があると。
この三部作は、マルセル・パニョルの初めての散文です。
作者はこう言います。
「今はもうすぎさってしまったある時代についての思い出であり、親を偲ぶ子の心のささやかな歌であるにすぎない」
それに対して、瀬田先生はこう言います。
引用
日常の細部を淡々とつづっているにすぎない。しかし、抑制のきいた描写は、かえっておしかくした感情の波を私たちの胸底にかきたてずにはおかない。
第一巻『父の大手柄』
第二巻『母のお屋敷』
第三巻『秘めごとの季節』
ネタばれになるので、あらすじは書きませんね。
引用
巻の構成もまた、父(社会)、母(家族)、自己へ、一種の形成への漸層が意図されているだろう。しかし教訓は一切筆にとらない。そのためにここでも、かえって読者は胸にひびくうったえをきくことができる。
マルセルの感受性に共感する部分が随所にあります。
その中で、私が特にあげるなら、山の別荘で友達になった土地の少年リリとの友情が描かれている所。
町に戻って日々を過ごしているマルセルのもとに、ある日、リリから手紙が届きます。初めての手紙。
小学生用のノートを破いた三枚の紙に、字の大きさは不ぞろい、つづりの間違いもいっぱいあって、インクの染みもある手紙です。
マルセルは、何度も読み返し、宝物としてしまっておきます。
そして、町へ行って美しい便箋を買ってきて、下書きをして二度読み返し、清書します。優等生の完璧な手紙です。
その手紙を出そうとして、考えます。それから、ノートの紙をびりびりと引きちぎり、字の大きさを不ぞろいに、つづりの間違いをあちこちにちりばめて、手紙を書き直し、インクの染みまでつけて、投函するのです。
忘れていたことを思い出させてくれる小説でした。
大人にも、もちろんこれから大人になる人たちにも是非読んでもらいたいと思います。