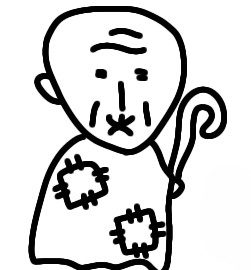年が明けて、今年初めての図書館のお話会の報告をします。
寒い中、来てくれたのは、子ども11人、大人10人でした。
手遊び おもちやいて~
おはなし 「おもちホイコラショ」『語りの森昔話集4』語りの森
〃 「ねずみじょうど」『おはなしのろうそく3』東京子ども図書館
絵本 『十二支のお節料理』川端誠/作 BL出版
〃 『ピーナッツなんきんまめらっかせい』こうやすすむ/文 中島睦子/絵 福音館書店
〃 『あのこはだあれ』北村人/作絵 岩崎書店
手遊び さよならあんころもち
たくさん子どもたちが来てくれたけども、小さい子が多くて、貼りだしてある予定では「ねずみじょうど」でしたが、ヤンさんが「おもちホイコラショ」を語り始めたので、小さい子どもに合わせて話を変えられたんだなと思っていました。
でも、続いて予定通り「ねずみじょうど」を語られたので、話が聞けてうれしいけどもびっくりしました。
というのは、自分なら「ねずみじょうど」はとてもできないから。
あとで聞いたら、ヤンさんも「聞くのは無理かもと思ったけれども、本日の予定は「ねずみじょうど」だからやってみた。修行です」とおっしゃったので、ヤンさんが修行といわれるならわたしはただただ「ははあぁぁ~」とひれ伏す気持ちになったのでございます。
でも後ろから見ていたら、難しいとはいいながらも、子どもたちはだいたいは聞いていたように思います。
動じずに最後まで語るヤンさんの力量ですね。
たぶん初めて来てくれた親子だと思うんですが、終ってからお母さんが絵本を三冊とも借りていかれました。
絵本のことをヤンさんにいろいろ話しておられたようですが、お話会に心をつかまれた様子だったのでうれしいことです。
この辺りは雪が降るほどではないけれどもここ最近寒くて、昨日は強風で風の音が怖いほどでした。
しばらく寒いんでしょうね~(-“-)
でも、図書館はあったかいから、土曜日のお話会にたくさん来てくれることを願っています(^O^)/