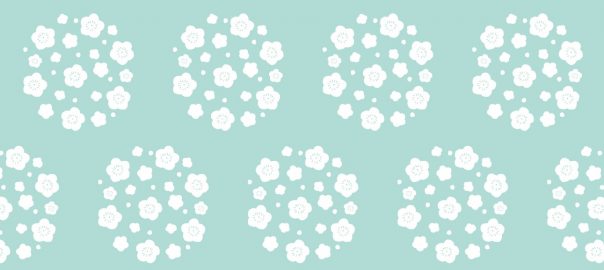今週火曜日は、日中はいちにち雨でした。
時々激しく降る雨に驚き、しかしうっとうしいなと思う間もないような、予定を一時間も超過するほど盛りだくさんの再話クラスでした。
再検討
「天狗のうちわ」(原題:「鳥うちわ」)『丹波和知の昔話』稲田浩二/編 三弥井書店
「聖アントニウスがこの世に火を持ってきた話」『新装世界の民話13地中海』小沢俊夫/訳 ぎょうせい
「黄金の騎士」『新装世界の民話19パンジャブ』関楠生/訳 ぎょうせい
新作検討
「狩人と三人の友だち」(原題:「弓の名人と友だち」)『ソビエト昔話選』宮川やすえ/編著 三省堂
書くことがたくさんありすぎて、1話ずつの内容を書くことはできませんが、わたしが担当だった話で痛恨のミスがあったことだけ書きます(´;ω;`)
「黄金の騎士」を耳で聞いてもらって確認してもらおうと、必死で何とか覚えて語りました。
この話は、話型がAT530「ガラス山の王女」なんです。
再話の中に〝ガラスの山は、すっかり氷におおわれた、鏡のようにつるつるの険しい山だったのです。〟という一文があります。
その説明の前後に、〝ガラスの山〟という言葉が何度も出てきます。
ガラスと氷と鏡という三つの言葉が「なんかおかしい」と思いながら、原話がそうなっているから仕方がないと思ってそのまま覚えましたが、ヤンさんの「これはガラスじゃなくて氷の山じゃないか?」というご指摘で原話を見ると、原話にはガラスという言葉がなかったんです!Σ(・□・;)
AT番号を調べた時のわたしの思い込みでガラスの山にしたのを、脳内で記憶のすり替えが起こって原話通りだと思い込んでいたということが判明しました。
今まで以上に自分で自分が信じられないことにショックを受けました。
笑って通り過ぎていいんでしょうか?
再話については、原話を何度も、ゆっくり急がず確認しながら再話していくしかないのですが、果たして日常生活で、わたしはいったいこれからどうしたらいいのかと、しばし遠い目をして地平線を見つめたのでありました。
「聖アントニウスがこの世に火を持ってきた話」と「黄金の騎士」は今回で完成しました。
完成稿は、あとで秘密基地にアップされますので、見られるかたはご覧ください。
「天狗のうちわ」と「狩人と三人の友だち」は次回で再検討します。
次回は5月28日です。
来年度から再話クラスは隔月になります。
痛恨のミスがあったとしても、やっぱり再話の勉強は楽しいです(*^。^*)
次回の勉強会も楽しみです(^O^)/