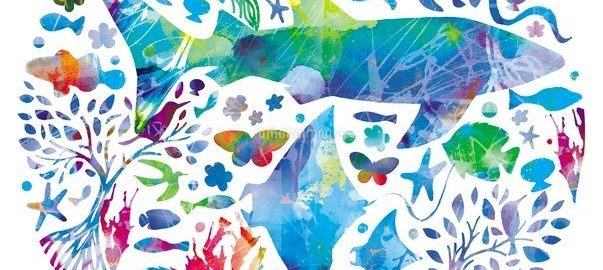今年は前代未聞の早い梅雨明けとなり
この日は朝から蒸し暑く、会場のクーラーが効いてくるまでは
各々が何かでパタパタとあおがずにはいられない~(;・∀・)
そんな中、語りクラスが行われました。
手遊び歌(カエルにちなんだものとのリクエストより)
♪雨だ、雨だ
♪カエルの夜回り
*どちらもYouTubeで検索すると多少違いますが視聴できます
語り
1.あなのはなし/『おはなしのろうそく4』/東京子ども図書館
2.おばけ学校の三人の生徒/『おはなしのろうそく28』東京子ども図書館
3.はしぼそがらすの神/『語りの森昔話集6』/語りの森
4.トリレヴィップ/『子どもに語る北欧の昔話』/こぐま社
ヤンさんの語り
5.忠実なヨハネス/『語るためのグリム童話1』/小峰書店
お話の背景を知ることは、語り手自身がイメージしながら語る時に大いに必要になります。外国のお話はもちろんの事、今回の語りにあった「アイヌ」のお話は、その生活様式や文化、信仰などがかなり違います。
そんな時、民族学博物館へ足を運んでみることで、とっても参考になるものが観れるとのこと。こちら➡
すでにお話の中にしかない、過去の文化に触れることも含めて「もっと広い世界を見たい」という想いで私も行って参ります!なかなかに見どころが多そうですが、中にレストランもあるみたいですので、休憩をはさんでゆっくり見て回りたいです❤
8月は勉強会はお休みですので、それぞれにご興味のあることを楽しまれて、それがお話語りにも良い影響を及ぼすことでしょう。
次回の語りクラスは9月9日(火)です。
みなさま、とにかくお元気で、楽しい夏をお過ごしください!