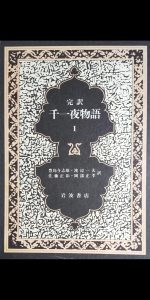先週、左ひざが動かなくなってね(;´д`)ゞ
もともと右ひざが悪くって、昔手術もしてるのね。
そのときと同じ痛さが左ひざに来た。
〇キソニンが効かない。
一日に3回も飲んでるのに!
わたし何か悪いことをした?
何のバチが当たったん?
何の呪いや?
こんなときは、ぜんぜん冷静になれない。
魔女の呪いにちがいないと確信する。
きのう、やっと近所の整形外科まで行くことができました。
先生「レントゲンで見る限り、軟骨がちょっとへってるけど、たいしたことないですね」
わたし「どうしたら治りますか」
先生「減った軟骨は元に戻らないけど、そのうちなじんできますわ」
なじむ?
薬で痛みを散らしながら、なるべく動かすようにすると、潤滑油のようなものが出てきて、なじむそうです( •̀ ω •́ )✧
なじむ
年寄り向きの、ええ言葉や。
その間の残酷性や初級クラスの勉強会も、子ども園のおはなし会も、頭の中の半分は痛みのストレスで満ちていて、集中力がなくて申し訳なかったです。
緊急で治療してくださったメンバーや車を出してくださった仲間たち、ほんとにありがとうございました。