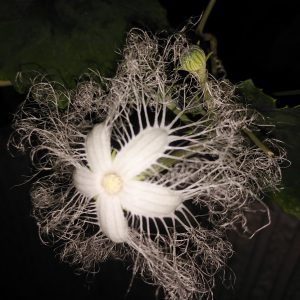残暑めっちゃ厳しき折からo(* ̄▽ ̄*)ブ
娘「こんなに暑く感じるのは、年とったからやろか」
わたし「いや、あんたが子どもの頃はこんなに暑くなかった」
娘「ほんま?」
で、アメダスで調べた。
わが市の9月4日の最高~最低気温
2020年31.8~24.7
2011年28.4~22.3
2000年30.2~17.5
1990年31.2~19.4
1980年30.6~19.8
最低気温が確実に高くなってる~
20年前には、朝夕はすごしやすいねっていってたんや。
8月平均気温
2020年29.3
2010年29.3
2000年27.9
1990年27.4
1980年24.9
ほらね、温暖化は確実。
年とったからやない。
何でも自分のせいにしたらあかん。
あ、温暖化も回りまわって自分のせいか╰(‵□′)╯
**********
今日はおはなしひろば更新。
鹿児島の話で「山神さま」
聞いてね~
*********
今日は、オンライン日常語入門講座。
伝承の語り手の語りを音声で聴いていただいたんだけど、聞きづらくってごめんなさい。
改良の余地ありね。