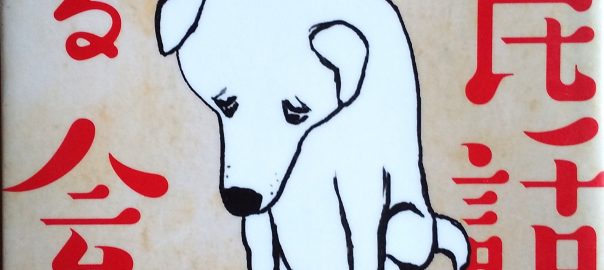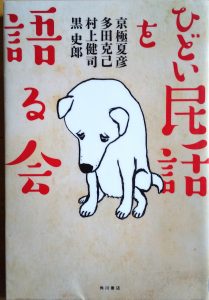今週の大人のためのおはなし会(16日金)にむけて、「馬方やまんば」をもどしています。
・・・出典は『日本の昔話5』おざわとしお再話/福音館書店
この話は、2004年に小学5年生に向けて語ろうと、「母の目玉」とセットで覚えました。
もう22年育ってきたんやなあ、と、感慨深い。
幼児から大人までたくさんの人に語ってきました。
前半は、馬方がやまんばに追いかけられる、いわば鬼ごっこの場面。
手に汗握るドキドキは、自分も子どものころ経験してるから、しぜん、リアリティが生まれる。で、子どものドキドキと、馬の足を切って投げるという現実にはあり得へんけど、夢の中やったらあるよなあって、子どものやっぱりリアルな驚きが、語り手を乗せてくれる。
語るたびに子どもといっしょにドキドキしてびっくりするうち、おはなしはわたしの中でしかと根を張る。
後半は、いろりの上の梁にかくれる、いわばかくれんぼうの場面。
前半が「動」なら後半は「静」・・・このはなし、構成がうまいなあ
ここでは、いろりに火をおこすこと、甘酒をあたためること、背あぶりすること、もちを焼くこと(以上やまんばの行動)と、梁にかくれること、屋根から茅をぬいてそれを使って飲み食いすること(馬方の行動)を、語り手がリアルに想像できることが、話の肝になる。
とすれば、語り手の想像力と表現力が試されるわけね。
もう何年も前に民族学博物館のツアーで白川郷に1泊したことがある。
ほんとは2泊のはずが、1泊で切り上げになったわけは、道中雪が降り始め、着いたときには大雪で、12月にこんなに降ったことがないといって、地元の人たちが、雪対策に大忙しで、お客の相手はしていられないから帰ってくれといわれたから。
大雪の中、小さなバスで荘川のほとりを走るの、恐かったよ~
それはさておき、とりあえずその晩は合掌造りの大きな家に泊まったの。
寒かったから、いろりの周りにみんなで集まって、地元の人たちと会談。
おおきないろりでね、めっちゃ大きな薪を放りこんで、火をたく。その煙いこと!暖かいこと!
寝る前にくるりとうしろを向いて背あぶりすると、芯まで温まって、ひと晩じゅう暖かいのよ。
あのときの外気の寒さと、いろりの暖かさ、外界と遮断された静けさが、「馬方やまんば」の後半を語るとき、わたしの中に再現されるの。
何度も何度も語り、伝えているうちに、それはわたしの中に根を下ろす。
レパートリーの1話1話に育ちがあって、それが楽しい。それが語り手の幸せやと思います。
******************
きのうのホームページ更新は《外国の昔話》
「相棒」です。
真面目なような笑いばなし?