なんか忘れてるなあ。
そうや、真庭市のやってるコミュニティーバスのことやった~
じつは、自転車での怪我が七割がた治った時点で風邪ひいちゃって、おはなし会三つもキャンセルして、めちゃ落ちこんでて、やっと今怪我も風邪も八割がたよくなったとこです。
それで、あのうるわしき蒜山高原のこと、思い出した次第。
真庭市が、住民のためのバスを運行しててね、蒜山高原から中国勝山まで乗ってきたのです。
だいたい1時間半の旅。たった200円!
写真は勝山の旭川からの風景。
まんなかに見えてるのは、酒蔵の煙突です。
勝山はこじんまりした落ち着いた城下町でした。
一時間ほどゆったりと散策。
JR勝山駅の近くに、喫茶店。
シフォンケーキがおいしかったよ。
それと、200年以上続くお菓子の老舗「古見屋羊羹」の田舎羊羹、絶品。
有名なのは「高瀬舟羊羹」なんだけど、わたしは、ちょっと固い田舎羊羹がおいしかった。
旭川は、源流が蒜山にあって~って、書きましたよね。
電車や自動車のない時代は、船がいちばん速い交通手段だったんですよ。牛馬よりも。荷物も大量に運べるしね。
で、川。
高瀬舟って、京都だけじゃないのです。
小型の船で、日本全国にあったの。
中国山地から瀬戸内海へと山間地を流れる川では、小型の高瀬舟が活躍してたんやね。
写真は、その港。船着き場です。
橋の上にヤンがいる。
山あいの集落をめぐって走るコミュニティーバスの旅、いいですよ。
土地のおばさんたちのおしゃべりは暖かい土地の言葉だし。
景色はいいし。
とちゅう、湯原温泉を通るし~
蒜山高原をぬけたところに、魅惑的な風景を見つけました。
ただ低い山と田畑と道があるだけなんだけど、胸がしめつけられるような郷愁。
来年はあそこへ行こう。
ヤン
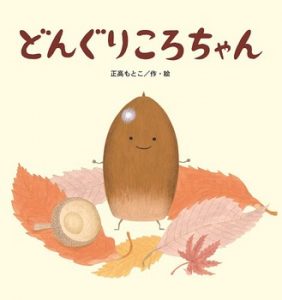
 蒜山高原には、お化けがいます。
蒜山高原には、お化けがいます。 ほとんどの見どころは、今回までにもう見終わってたんだけど、まだ行ってなかったのが、蒜山郷土博物館。
ほとんどの見どころは、今回までにもう見終わってたんだけど、まだ行ってなかったのが、蒜山郷土博物館。





