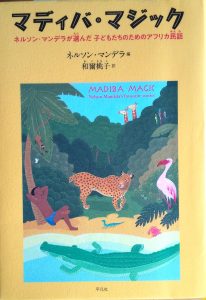4月22日(月)
こども園
4歳さん 1クラスずつ2回
手遊び ろうそくぱっ
おはなし「ひとり、ふたり、さんにんのこども」『おはなしのろうそく26』東京子ども図書館
てあそび ろうそくぱっ
5歳さん 1クラス
手遊び ろうそくぱっ
おはなし「ついでにペロリ」『おはなしのろうそく6』東京子ども図書館
絵本 『ぼんやりしてたら』五味太郎/ポプラ社
手遊び ろうそくぱっ
今年度最初のおはなし会。
ひとつ学年が大きくなって、きっとがんばってるんだろうな。
お話を聞くのも、4歳さんは、とってもがんばってる感じがしました。
でも、ちゃんと、次を言い当てながら聞いてましたよ。
でもつかれちゃって、いつもの「みじか~い」の声がちょっとちいさかった(笑)
それで、オマケのおはなしはしませんでしたよ。
5歳さんは、めっちゃうきうきしていました。
おはなしも笑ってましたが、絵本になると、「うそや!」「それはないわ!」って爆笑に次ぐ爆笑。
でもやっぱり疲れちゃって、いつもの「もっかい!」は出ませんでした(笑)
しばらくして慣れて力が抜けてきたころに、ゴールデンウィーク。
先生「また最初からです」
そうね、毎年のことですね(^///^)