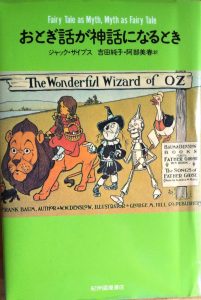
本の紹介です。
ジャック・ザイプス著 吉田純子・阿部美晴訳 紀伊国屋書店 1999年
おとぎ話っていうのは、昔話とか民話とか、妖精物語とかのことです。
わたしたちは、グリム兄弟が、彼らの意図・目的があって、口承や書承の物語を再話したって知ってますよね。それは、近代国家の成立っていう、時代の要請でもあった。
ところで、ディズニ―は、グローバルな資本主義の意図のもとに、グリム童話等をアニメ化した。
そうやって、おとぎ話は、時代によって変化させられてきた。
その流れの中で、本来の物語の力はどこへいってしまったのか?
というようなことを考えさせる本、だと、思う。
本の帯に、こう書いてあります。
おとぎ話を殺したのは誰?
ーグリム兄弟やディズニーがかけた呪文を解き、物語の力を取り戻すためにー
ストーリーテリングというのは、物語の言葉でその場の人びとをひとつにまとめて、経験から生まれた知恵を伝えるもの。
ううむ、むずかしいな。少なくとも、それは語られてこそ生きる物語ってことかな?
ちょっと手に負えない部分もあるので、現段階で紹介するのは無責任かと思うけど、みなさま、読んでみてください。そして、考えたことを教えてください。
目次を紹介します。
1おとぎ話の起源
2ルンペルシュティルツヒェンと女の生みの力の衰退
3ディズニーの呪文を解く
4アイアン・ジョンについての神話を広める
5アメリカの神話としてのオズ
6現代アメリカのおとぎ話
4~6で紹介されている作品で読んだことのないものがあるので、ちゃんと読んでから、もう一度勉強したいと思っています。
画像は、「オズの魔法使い」の表紙絵です。
***********************
猛烈に暑いって思ってたら、こんどは猛烈に雨が降っています。
各地のみなさま、どうぞお気を付けください!
今日のおはなしひろば更新は「阿波のせいざえもんと京の古金屋でんべえ」です。いい話です。聞いてくださいね。












