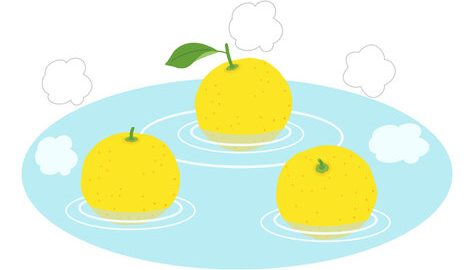11月末に開催されました「貧乏神大会」の余韻が残る中、12月の勉強会が始まりました。
その前にヤンさんから貧乏神大会について一言。
☆同じおはなし(テキスト)でも語る人によって違うおはなしになる
⇒語る人の想いが込められるため
⇒語り手の数だけおはなしがある
⇒語りクラスは一人一人その人のおはなしを完成させるための勉強会
一度にあれだけの貧乏神を聞く機会は初めてでしたが、全く飽きることなく、次はどんな貧乏神?と楽しい時間でした。同じおはなしでも「さっき聞いたおはなしやん」となりませんでしたね。
この気持ちを忘れず、日々精進していきましょう!
👐手遊び(山形のわらべ歌) 『レブラディ ボーラディ♪』👐
語り
➀「おいしいおかゆ」 『おはなしのろうそく3』/東京子ども図書館
➁「山寺の化けもの」 『日本の昔話1」/福音館書店
➂「鬼の面 お福の面」 『語りの森昔話集6』/語りの森
④「ゆうかんな靴直し」 『子どもに語るイタリアの昔話』/こぐま社
⑤「トリレヴィップ」 『子どもに語る北欧の昔話』/こくま社
ヤンさんの語り
「さるの婿さん」 『語りの森HP』⇒こちら
個人的に特に「なるほど~」と感じた「おいしいおかゆ」について報告します。
Nさんは「おいしいおかゆ」を図書館で語る予定で発表されました。
アドバイスとして、小さい子どもに語るときはテキストを変更する必要があるそうです。
「、」で文章がつながっており、一文が長すぎるため、小さい子どもにはイメージができません。「、」を「。」に変えればいいそうです。
例えば、
*すると、ひとりのおばあさんに会いましたが、そのおばあさんは、女の子のこまっていることをちゃんと知っていて、ちいさなおなべをひとつ、その子にくれました。
→すると、ひとりのおばあさんに会いました。そのおばあさんは、女の子のこまっていることをちゃんと知っていました。そして、ちいさなおなべをひとつ、その子にくれました。
*そのうち、台所がおかゆでいっぱいになり、家のまえの道も、おかゆでいっぱいになり、それから、となりの家がおかゆでいっぱいになりましたが、おなべは、まだ、ぐつぐつ、ぐつぐつ、にています。
→そのうち、台所がおかゆでいっぱいになりました。それから、家のまえの道も、おかゆでいっぱいになりました。それから、となりの家がおかゆでいっぱいになりました。それでも、おなべは、まだ、ぐつぐつ、ぐつぐつ、にています。
「。」に変更するだけで、おかゆがあふれ出す情景が自然にクレッシェンドになります。
ヤンさんからの経験から、1.2年生までは変更したほうがよい、想像する力がついてくれば、ろうそくのテキストのまま語ればいいそうです。
私も一度低学年に語ったことがあるのですが、全くうけずに終わり、それ以来封印しているおはなしでした。
なぜだろう?と思っていた疑問がすっきり晴れ、今後語るおはなしにも活かそうと思いました。
10月の語りクラスで発表した「金の鳥」を小学5年生に語ってきましたので、ここで報告します。
一クラス目、静かに聞いてくれていましたが、反応があまりなく………大好きなおはなしという感情が出過ぎた?きつねのアドバイスは真剣になりすぎ?と反省しつつ、”語り手はおはなしを手渡すだけ”、”聞き手が自分でイメージして楽しむ”を意識して、二クラス目を語りました。
・末の王子が何度も失敗する→「またやん、あほやな」
・きつねが自分を撃ち殺して首と前足を切り落とす→「えっ?!」(全体の雰囲気が引き締まる)
・井戸のふちに腰をおろしておしゃべりをしよう→「(首を横に振りながら)だめだめ」
・2人の兄さんは処刑されました→「良かった~」
・それからはみんなは生きている限り幸せにくらしました→「満足」
子ども達の次々に変わる表情を見ながら、楽しく語れました。
練習するたびに「ええはなしやな」と思っていましたが、今回は初めて子どもに語って、更に好きになりました❤
次回は2月10日(火)です。少し早いですが、よいお年をお過ごしください☺