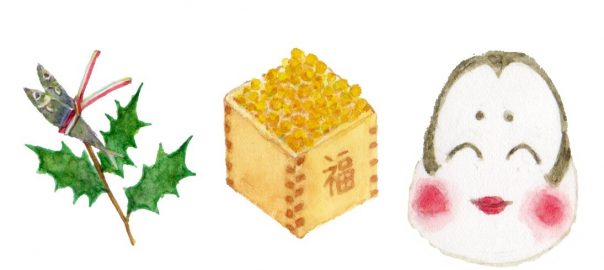こんにちは。
ドラマの見過ぎで目が疲れていて涙目なのかと思っていたら鼻もムズムズしていて、どうやら花粉症がやってきたようです。
今年は飛散量が多いそうで恐ろしい(-_-;)
2月のプライベートレッスンの報告です。
1日目
再話
「貧乏神」
原話『新しい日本の語り5藤原ツヂ子の語り』日本民話の会 悠書館
貧乏神の話をずっと追いかけておられる、その新作です。
なんと、藤原ツヂ子さんの音声が残っております!
語りの森HPでもリンクを張っている〝東アジア民話データベース〟で聞くことができます(^O^)
東アジア民話データベース → こちら
トップページ → 日本各地の民話を聞いてみよう → 東京 → 藤原ツヂ子さんの語り
一番最初に「貧乏神」が出ています。
再話するときに音声を聞けるというのはめったにないパターンで貴重ですね。
原話の語り手さんの語られた話を本を編集した民話の会のかたがどういうふうに読む文章に変えられたかが分かりますし、それをもとにこんどは耳で聞いて分かりやすいテキストにするという作業をされたわけです。
語り手であるからできる作業ですし、やらなければならない作業だと思います。
とても勉強になりました。
参加者さんが貧乏神の話を全国から探しておられることも、すでに研究のようになっているんじゃないでしょうか?
原話をたくさん読むことはとても力がつくんですが自分はそれができていなくて、見習わなくてはと思いました。
2日目
テキストを日常語になおす
「舌切りすずめ」『語りの森昔話集4おもちホイコラショ』村上郁再話 語りの森
小学校の低学年と幼児さんに語るために、助詞をあえて抜かない個所をのこして、日常語のテキストになおしたそうです。
わたしも、幼稚園で日常語で語って「あ! 意味が分からないんだ」と思ったことがありました。
標準語だと分かるんでしょうが、地元でも小さい子は単語が違って分からないことがあるようです。
この「舌切りすずめ」は、すずめの名前が〝たろう〟なんですよ。
いろんな「舌切りすずめ」があって面白いですね。
語り
「マカトのたから貝」『子どもに語るアジアの昔話2』松岡享子訳 こぐま社
これ、わたしなんですが、4年生に語る予定です。
おはなしを始めたころに覚えて3年ほど語り、その後15年くらい語っていませんでした。
話を戻そうとテキストを読んでみたら、そのころは見えなかったものが見えてきたといいますか、手も足も出なかったであろうことができるようになったといいますか、テキストを整理する箇所を見つけましたのでいったん自分でやってみて覚え、ヤンさんにチェックしてもらいました。
その結果、より語りやすく聞きやすいテキストができてうれしいです。
昔話の語法の勉強を続けていてよかったと思う瞬間でした!
3日目
語り
「鉄のハンス」『子どもに語るグリムの昔話5』佐々梨代子・野村泫訳 こぐま社
去年の11月の中級クラスで他のかたがこの話を語られて、その時の講評と今回のプライベートレッスンの勉強で、わたしは語りもしないのにとても「鉄のハンス」を理解したような気になっています(笑)
ああ、語る当てもないのに覚えたい~~
でも、長い話だし、ほかに覚えないといけないのと、戻さないといけない話がある~~(´;ω;`)
みたいな気持ちを感じております。
語り手アルアルですね。
若い時みたいに力技で覚えられない自分の頭が恨めしいです。
語り手のみなさん、若いうちにたくさん覚えておいたほうがいいよ!
最後は愚痴になっちゃってすいません。
とはいえ、継続することが大事だしそれが難しいですよね。
細く長く続けられるように頑張るのがいいんだと思います。
では、また~~(^O^)/