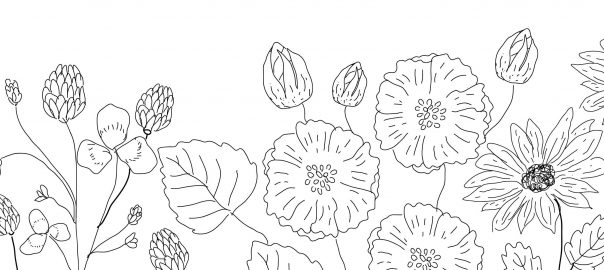もうすぐ、ハロウィンですね。
うちは、全く何にもしないんですが、お店の飾りや売り物がハロウィンだらけで楽しいです。
10/25の図書館のお話会の報告です(*^_^*)
始まり時間では人が少なめだったんですが、始まって間もなくすると人が増えて、参加者は子ども12人、大人9人でした。
手遊び く~るぽん
おはなし 「命のろうそく」『語りの森昔話集6』村上郁/再話 語りの森
〃 「ひとりふたりさんにんのこども」『おはなしのろうそく26』東京子ども図書館
絵本 『おばけときょうりゅうのたまご』ジャック デュケノワ/作 おおさわあきら/訳 ほるぷ出版
〃 『そしたらそしたら』谷川俊太郎/文 柚木紗弥郎/絵 福音館書店
〃 『おおいすくないどっちどっち?』鹿子木康弘/作 La ZOO/絵 PHP研究所
〃 『おべんとうなあにかな?』小林治子/絵 ひかりのくに
〃 『ちゅるちゅる』視覚デザイン研究所/作 内山悠子/絵 視覚デザイン研究所
手遊び さよならあんころもち
「命のろうそく」は、ヤンさんが始めるときに「ちょっと難しいかもしれへんけど…」と一言いわれたので、わたしも気合を入れて聞こうと気が引き締まりました。
別にそんな必要はないのにです(笑)
常連さんもいましたが、小さい子どもさんもいたから「命のろうそく」は、たしかに小さい子には難しいかもしれません。
でも後ろから見ていたら、大方の子どもはよく聞いていたと思います。
さすがヤンさん、わたしならとても決断できないでしょう。
そして、小さい子どもさん用の話をひとつして絵本にいくという安全策をきっととると思います。
ああ、修業は続く…。
でも、子どもたちのおはなしを聞きたい気持ちや、楽しみにしている気持ちには応えたいと思うし、異年齢の子どもが集まる場所ではほんとにプログラムが難しいですね。
自分の持ちネタの範囲が限られている中では限界がすぐそこなんで、やっぱりいろいろ語れるように話を増やすほかないという、ず~~っと前からわかっている結論にたどりつくわけです。
記憶力低下と戦いながら頑張ります(笑)
『おおいすくないどっちどっち?』で、子どもたちはすぐにどっちか言ってたけど、わたしはよくわかりませんでした。
差があるように見えて、ほんとは同じじゃないのかなと思って見ていたんですが、そうじゃなかったみたいで、子どもの目ってほんとにすごいですよね~~(^O^)/