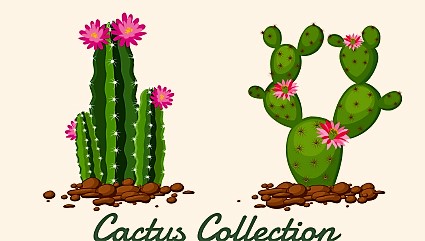こんにちは。
ここのところ、しばらくずっといいお天気が続いていたのに、ついに今日は雨です。
11月の日常語クラスの日はとってもいいお天気でした。
久しぶりにお会いできた方もおられ、お互い元気で会えるというのが何よりうれしいです。
この日のメニューは以下のとおりです。
語り
「話十両」『日本の昔話3』福音館書店
「やまなしとり」『日本・中国・韓国の昔話集2』国立オリンピック記念青少年総合センター
ヤンさんの語り
「まめとすみとわら」語りの森HPおはなしひろば → こちら
テキストを日常語に直す
「手なし娘」『日本の昔話3』福音館書店
「島をすくった三人兄弟」『日本の昔話3』福音館書店
「きつねの恩返し」『日本の昔話3』福音館書店
福音館書店の『日本の昔話3』からの話が4話もありますね。
1巻から4巻までが春夏秋冬の順番になっていて、5巻はどれにも入らないかオールシーズンオッケイの話が収録されているそうですから、やっぱりそうなんやと納得しました。
「ならなしとり」も秋の話ですし、ほぼ秋一色のお話会みたいですね。

やまなしの実を、ヤンさんがブログで上げてくれてましたね。
写真を撮られたときに、木にプレートがかかっていて「ヤマナシ」と書いてあったそうです。
おはなしのタイトルとしては、「やまなしとり」、「やまなしもぎ」、「ならなしとり」、「やまなしもぎ」(算数の、順列組み合わせみたい・笑)と類話や再話でいろいろになってますが、実としてはこの写真が本物だということで、イメージがはっきりしてよかったです。
ピンポン玉の大きさで、柄が長くて、まさに〝ざら~ン、ざら~ン〟と、風になりそうです。
ヤンさん、見つけてくださってありがとう!!
ブログの記事はこちら → ローカル列車の旅その4
「きつねの恩返し」で、きつねが変身するときに、宙で回転するんですね。
わたしは今までこの話をヤンさんの語りで聞いていて、回るのは❝クルッッッン、クルッッッン、クルッッッン❞くらいのゆっくりさでホールのロールケーキの方向で回ってました。
この日テキストを出した方は結構早くて、❝クル・クル・クルー❞くらいだったのでわたしは高速回転で若い元気なきつねをイメージしました。
そのことを発言したら、テキストを出した方は回転方向がロールケーキ型ではなくて、竜巻みたいにきつねが立ったままバレリーナのようにスピンしてたとのことでした。
他のみなさんも口々に、「○○だった~」と言われて、みんなが自分だけのイメージを持っていたのがわかりました。
面白いですねえ~。
それぞれに、いろいろ頭に浮かんでたんだと思うと楽しいし、笑えてほっこりしました。
昔話はそれぞれのイメージが違うことも楽しく共有できるという素晴らしさ!
楽しい勉強会でした✌(‘ω’✌ )三✌(‘ω’)✌三( ✌’ω’)✌