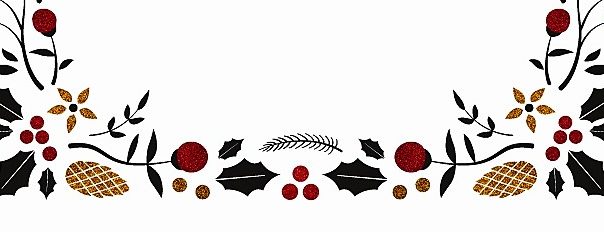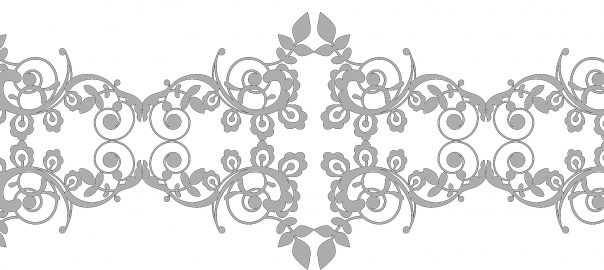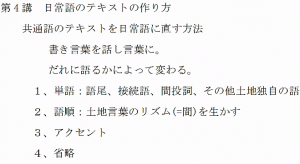寒波が来ておりますね。
日本海側は大雪だそうで、心配ですね。
遠くのほうに京都の北の方の山々が見えるんですけど、まっ白になってます。
今年最後のプライベートレッスンの報告です。
1日目
「ぽったりもち」語りの森ホームページ → こちら
日常語で語るためのテキストにされました。
元の共通語テキストと格闘していますと、使われている動詞とか登場人物の気持ちとかの細かいところにまで気になってきたりします。
それで、自分的にはこうじゃないかなと思って少し心情表現を足したくなる場合もあろうかと思いますが、今回はそれについて話題になりました。
昔話はできるだけ基本の動詞(食べる、笑う、行く、寝る等)を使い、心情表現はあまり使わない。
使うとしたら、泣く、淋しいなどに限定して用いられています。
これは昔話の語法に則っていて、昔話は行動で表して話が先に進んでいくからです。
そして、それを聞き手はそれぞれの心の中にそれぞれの心情を思い描くのです。
もし語り手が、例えば、あきれて、がっかりして、等の心情表現を入れてしまうと聞き手はそれだけに限定されてしまいます。
そのほかにもあるかもしれない登場人物の気持ち、いろんな気持ちが混ざっているかもしれない複雑な心の中を聞き手がイメージすることを奪ってしまいます。
こういうことを考えていくと、日常語テキストを作るということは再話することにもつながりますので、語りの勉強というのは同時進行でやることがいっぱいなんですね。
おはなしと格闘されているのがすごいなあと思いました。
2日目
「プレッツェモリーナ」語りの森ホームページ → こちら
5年生に語られるそうです。
これはイタリアのフィレンツェの昔話です。
グリム童話ですと「ラプンツェル」ですね。
類話ですが、おはなしの姿としてはかなり違います。
明るくて楽しいおはなしです。
「ぼくにキスしてくれたら、元通りにしてあげよう」なんて、こんなきざなセリフどの口が言うねん!って思いますが(わたしだけ?)、イタリアと聞いたらそれも納得ですね。
語りのアドヴァイスです。
語り手が、疑問を持ちながら語っていたり、細部のイメージをスルーして語っていた場合、聞き手もその箇所はイメージし辛いようです。
語り手が納得して語る、細部までイメージして語ることで、聞き手もイメージできるということを心にとどめて練習しましょう。
今回、語り手さんは主人公やその他の登場人物の人物像がしっかり設定されていて、聞き手はイメージしやすかったです。
いよいよ今日は仕事納めですね。
わたしは仕事してないんで関係ないんですけど、気持ちは年の瀬だと実感してきました。
スーパーでは、少し前から正月用品がどんどん増えてますし、特に何もしないと決めているのですが気持ちだけが追いつめられるような(笑)
今年はババ・ヤガーの勉強会も再開してうれしい事でした。
でも、まだまだソーシャルディスタンスを保たないといけないので以前通りということでは開催できません。
来年は、元通りになりますよう祈っています。
ではみなさま、どうぞよいお年をお迎えくださいませ。