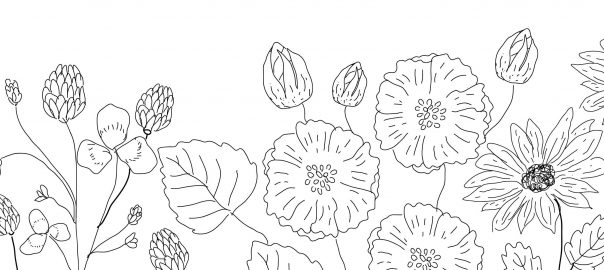朝晩がすっかり涼しくなって、長かった夏が過ぎて、ようやく秋を感じられるようになりましたね。
でも、最高気温は30度の日もあり、昼間はまだ暑さにおびえております。
体調を崩さないようにみなさんお気を付けください。
とはいえ、元気に9月も大人のためのお話会を開きました(*^_^*)
9月のテーマは❝オオカミ❞
おはなし 「三びきの子ブタ」『イギリスとアイルランドの昔話』石井桃子/編・訳 福音館書店
絵本 『セルコ』内田莉莎子/文 福音館書店
〃 『オオカミがとぶひ』ミロコマチコ/著 イースト・プレス
おはなし 「おおかみのおんがえし」『子どもと家庭のための奈良の民話二』村上郁/再話 京阪奈情報教育出版
手遊び ちーちゃんぱーちゃん
おはなし 「おおかみ神社」『子どもと家庭のための奈良の民話二』村上郁/再話 京阪奈情報教育出版
絵本 『ひとりぼっちのオオカミ』ケイティ スリヴェンスキー/文 BL出版
おはなし 「おばあちゃんのはなし」ジャック・ザイプス/著 阿吽社
絵本 『オオカミクン』グレゴワール ソロタレフ/作 ポプラ社
オオカミが出てくる昔話といえば、「三びきの子ブタ」と「赤ずきん」ではないでしょうか?
ということで最初は「三びきの子ブタ」ではじまりました。
これは悪いオオカミです。
子ブタを次々に食べてしまいます。
でも三匹目の子ブタは策を弄してオオカミをほんろうし、最後には鍋で煮て食べてしまいます。
悪者打ち取ったり!
「おばあちゃんのはなし」は、「赤ずきん」として知られるようになる前の、時代をさかのぼったら元はこんな話でしたというおはなしです。
「赤ずきん」の原型ともいう話で、オオカミではなくて狼男です。
聞き手の子どもを怖がらせて楽しませる話で、最後は逃げきって生き延びます。
面白いのは、「三枚のお札」のように、トイレに行きたいといってベッドから逃げ出し時間稼ぎをすることです。
自分にくくられたひもを外の木に結び変えて逃げるんです。
いっしょや~~ん!
そして日本の昔話はいいオオカミと怖いオオカミの話です。
日常語で語られました。
どちらも同じ奈良の昔話ですが、ちょうどこの日、奈良からいらしてくださった二人組のお客様がおられて、とっても喜んでくださいました。
初めてのお客様だったのでいろいろ話を聞かせていただき、喜んでくださっていたのでこちらもこの状況の一致に、メンバー一同とってもうれしかったです。
絵本もいろいろなオオカミが見られて楽しかったです。
『ひとりぼっちのオオカミ』は、人になつかないのがオオカミですが、人間と友だちになる最初のいっぴきを描いた絵本です。
ほかのオオカミとは違っていて、独りぼっちだったオオカミが人間に寄り添うことからだんだん人間の友だちの❝犬❞にかわっていったんだろうとのことで、なるほどなと思いました。
最初のいっぴきとは、ふつうとは違う個体だったんだと妙に納得しました。
みんなちがってみんないい、ですよね。
さて、来月からの日程とテーマをお知らせしておきますね。
10月17日(金)テーマ❝くだもの❞ おいしい果物がいっぱい出てきますよ
11月27日(木)テーマ❝猿❞ 動物シリーズのひとまず最後です
12月19日(金)テーマ❝音楽❞ 歌や楽器が出てくるおはなしと絵本、とにかく音楽いっぱいです
大人のためのお話会、次々に準備して、みなさまのお越しを待ってます~~♫