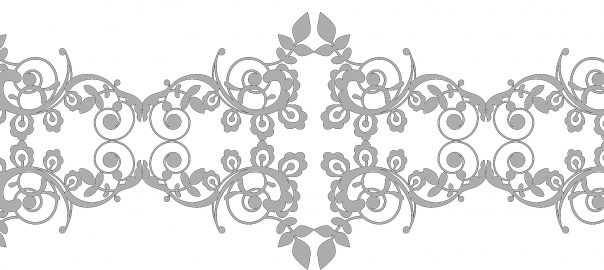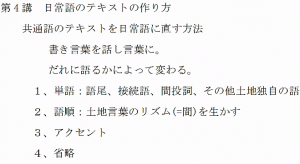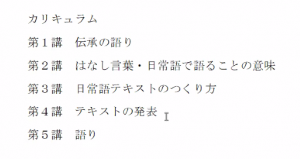早いもので、今年ももう一か月が過ぎました。
今日から2月です!
通常の勉強会はお休み中ですが、コロナ感染の心配のないオンラインのプライベートレッスンは、1月・2月も行います。
1月のレッスンの内容を報告します(^o^)
1日目
語り「魚がくれた子ども」 語りの森HP外国の昔話 → こちら
さらっと語らないで、しっかり語る箇所の指摘がありました。
それと、感情を示している台詞なのでそのように感情をこめて語ってしまいそうだけれども、この台詞の意味は聞き手が「誤解が解けたんだ!」と分かるところなので、感情を込める台詞ではないという指摘がありました。
教えてもらって、なるほどなと納得しました。
語り「六ぴきのうさぎ」『語りの森昔話集1おんちょろちょろ』語りの森
ひとりで続けて2話語られました。
すごい~!
1年生に、「三びきの子ぶた」と組み合わせて語るそうです。
2日目
日常語のテキストに変える
「佐渡の白つばき」『語りの森昔話集5ももたろう』語りの森
この話は「夢のはち」の類話で、「夢のはち」は全国に類話が分布しているそうです。
テキストを日常語に変えるときには、いろんな場面で主語のいらないことが多いです。
〝ふたり〟や〝みんな〟も消せることが多いです。
しかし、だからといってそれらが出てきたら消したらいいのかというとそうではないので、言葉では限定できないそうです。
3日目
語り「首の短い男の話」 語りの森HP日本の昔話 → こちら
アイヌの昔話です。
中学生に語られるそうです。
アイヌの昔話は独特ですし、風習も違いますから聞き手に分かってもらうように語るのは難しいです。
一度中級クラスで発表され、プライベートレッスンで再チャレンジされました。
語る前に、「アイヌの昔話は主人公の一人称ですすめる」と、さらっと言っておいたらいいということでした。
アイヌの昔話は、ちょうど昨日アップされていますのであわせて読んでみてくださいね。 → 「さきぼそがらすの神」
日常語の語り「きつねの茶釜」『日本の昔話2したきりすずめ』福音館書店
おもしろかったです~~
笑い話なのでおもしろくて当たり前なんですが、台詞が身近な普段使っている言葉になるとなんでこんなに面白く感じるんでしょうかね?
でも、語るほうとしては、やっぱり語尾が定まらないという難しさがあったようです。
オンライン日常語の語り入門講座でも同じでしたね。
これは、根気よく何べんも何べんも繰り返して練習し、自分の声を自分の耳で聞いて確かめる。
言いやすい方に流れるのではなく、自分の感性でもって、心地よい着地点を探し当てる。
こうやって言葉を決める・固めるしかないということですね。
コロナのために学校のお話会も中止の所が多いようです。
お話会も勉強会もなしという状況でも、残っているお話会を大事にして、そして勉強の機会をのがさずにプライベートレッスンを受けてくださるかたたちの姿を見せてもらって、元気をいただきました。
ありがとうございました<(_ _)>(^o^)/