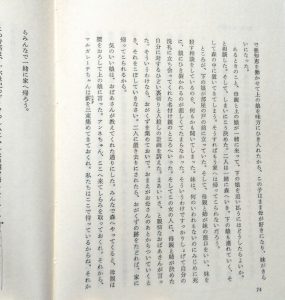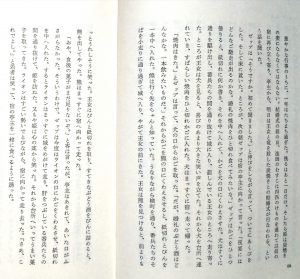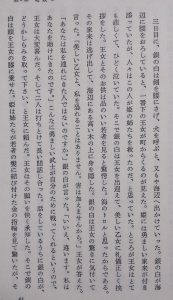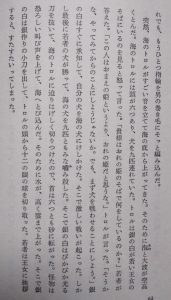マックスリュティ『昔話の本質』報告
第4章 地の雌牛ー昔話の象徴的表現つづき
わあ、急に雨が降ってきた。
まだ梅雨は明けてなかった
失礼しました
きのうの続きです。
マルガレーテちゃんは、名付け親のアドヴァイスで無事森から帰って来られましたね。
同じことが、3回くりかえされます。
しかも同じ言葉で。
同じ言葉だから、聞いていて、話にはっきり区切りがつくのです。
2回目は、マルガレーテちゃんはもみがらをまきながら森に入って行きます。
3回目は、麻の実を持って行きます。
すると・・・
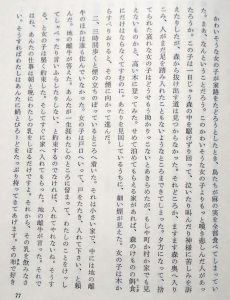
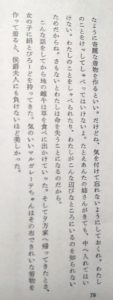
地の雌牛って、いったい何でしょう。
リュティさんも知りません。
16世紀、この話が記録されたときには、いちいち説明しなくてもみんなが知っていたんですね。
ゲーテも知っていたそうです。えっと、18世紀から19世紀の人ね。
でも、20世紀にはもうわからなくなってる。
リュティさんは、それでもいいんじゃないと言います。
意味は分からなくても響きになじみのある単語は、珍しいことがらを分かりきった調子で語る昔話の雰囲気によく合うからって。
なるほどね。
で、マルガレーテちゃんは地の雌牛を大喜びで受け入れますが、聞き手の私たちも大歓迎します。
雌牛が人間のことばをしゃべることに、全然びっくりしません。
これが伝説や聖者伝と違うところね。
もし雌牛がしゃべったら、伝説や聖者伝では「奇跡」として描くけれども、昔話では、奇跡は当たり前。
あらゆるものがあらゆるものと関係を結びうること、これが昔話における本来の奇跡であり、同時にまた自明の事柄でもある。
動物や彼岸の存在と言葉が通じることについては、《昔話の語法》一次元性のところで説明してるので検索してみて。
地の雌牛は、彼岸の存在。
それは了解ですね?
地の雌牛はマルガレーテちゃんにミルクと布をくれます。
ミルクは、雌牛だから当たり前として、絹とビロードという高価な布をくれます。
この絹とビロードについて、リュティさんは、人の手の加わった貴重な品物といいます。
昔話には、人工的なものがよく出てくるのです。
たとえば、伝説では、巨人や小人は山の洞穴に住んでいるけれど、昔話では宮殿や小屋にすんでいます。
ほら穴というのは自然の中にあって、想像すると、不確定な線で描かれます。型がない。
宮殿や、地の雌牛の小屋は、直線。しかも、垂直な線と水平な線でできています。
幾何学的、抽象的な鋭さや、さらにいえば明白さ、純粋な型式で描かれる。
ね、昔話の好む文体ですね。
はい、きょうはここまで。
**********
きょうは午後からおはなしひろばを更新しますね~