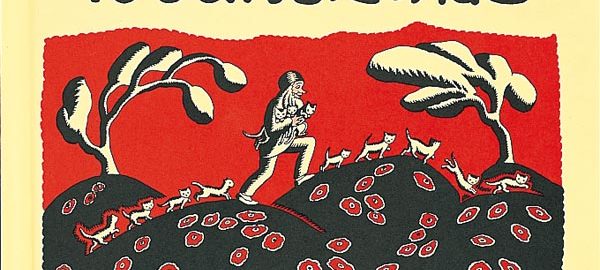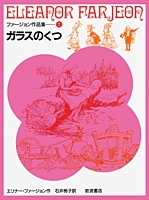わたしたち、ずうっとこれで守られてきたんやね
憲法記念日やから、読んでみよう ^0^
語釈付きだよん。
++++++++++
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
協和:互いに心を合わせて仲良くすること。
自由:自分の心のままに行動できる状態。
恵沢:めぐみ。
主権:事柄の最終的な決定をする権力。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
国政:国の政治。
厳粛:ごまかしやふまじめを許さない、きびしさのあること。
信託:信用して任せること。
権威:下位の者を強制し服従させる威力。
権力:他人を強制し服従させる力。
福利:幸福と利益。
享受:受け収めること。
原理:根本の理論。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会におゐて、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
専制:独断で政治を行うこと。
隷従:人の言うなりになること。
偏狭:心の狭いこと。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
++++++++++
すごいね。
「日本国民」って、私たち一人ひとりだよ。
私たち、これに守られてきたけど、逆に、守ってもきたんだ。すごい!
ヤンは中学3年のとき、社会の時間にこの前文と、9条と、25条を暗唱させられたの思い出した ^3^
今日のレパートリーの解凍は「ひとりふたりさんにんのこども」o(*^@^*)o
これは夕方の写真