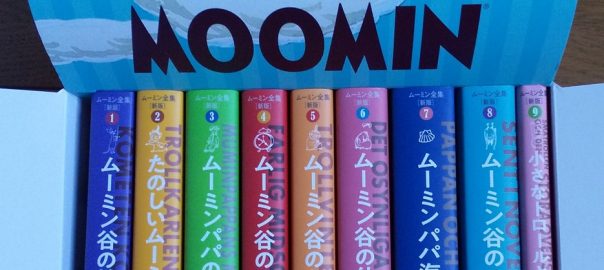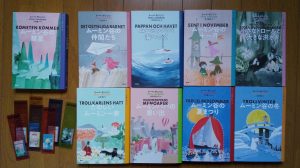マックス・リュティ『昔話の解釈』を読む
第4章「死人の恩返し」
なんだか物騒ですね。不気味ですね。
でも、死人だって恩返しをするのです。狐や鶴ばかりではありません。
ところで、クイズです。次のグリムの昔話に共通することは何でしょう?
「七羽のからす」「六羽の白鳥」「かえるの王さま」「兄と妹」「いばら姫」「白雪姫」
答えは・・・
*
*
*
*
じゃーん!
*
*
*
*
*
救済がテーマになっていること~
救済っていうのは、魔法の害から救い出すこと、魔法によって変えられた姿をもとへ戻すこと、呪いを破ること。
先に上げたグリム童話のような、救済をテーマにしている昔話を救済話っていうそうです。
でも、広い意味でいえば、昔話はほとんどすべて救済話だとも、リュティさんは言っています。
そして、これらの話は、なぜ魔法にかけられたか、なぜ呪いを掛けられたかということよりも、どうやって救済されるのかということに、力点が置かれています。
このことは、昔話が人間をまさに救いを必要とする者と見なしていることを示していると言います。
この昔話の態度は、キリスト教に近いとも言っています。
人間は援助と救済を必要とする。
このテーマは、死人の恩返しの類話に、いろいろと形を変えて出てきます。
この話では、主人公だけでなく、援助者の死人自身も救済を必要としています。
ここで、アスビョルンセンとモーによるノルウェーの昔話にある「仲間(みちづれ)」を見ていきます。
読みましたかあ~
こちら⇒「旅の仲間」
これの冒頭~2ページ目10行目まで、リュティさんの解説。
行きますヾ(•ω•`)o
あとから追いかけてきた男=旅の仲間こそが、主人公が助けた死人なんですね。
この死人がいなければ、主人公は、夢に見たお姫さまと結婚できません。
テーマ1
主人公は無一文になることによって、それと知らずに、自分の目的を遂げさせてくれるただひとつのもの、つまり超自然的援助者を手に入れる。
これ、事物は反対物に転化するっていうあれです。
かしこい兄さんではなく愚か者の末っ子が命の水を手に入れるとか、灰かぶりのきたない娘こそが王さまと結婚するとか、昔話は好きですよね。
テーマ2
目下の義務に専念することから生ずる有効範囲の思いがけない広がり。
主人公は、お姫さまさがしをさしおいて、死人を助けますね。目の前のことに専念しています。そのおかげで、かえって目的(お姫様発見)に近づくことになりました。
テーマ3
自己を放棄することができる者のみが自己を獲得することができる。
主人公は、お姫さまさがしのために、家も畑も全部売り払います。そのお金を、ほとんどぜんぶ死人のために使いますね。ふつうなら、考えられませんね。
捨てることのできる者のみが天国を手に入れるという意味で、やはりキリスト教に近いと、リュティさんは言います。
はい、おしまい。
「旅の仲間」、最後まで読んでね。あ、夜に聞いたら寝てしまうよ。長いから(笑)
*********
きのうは、おはなしひろば。
「干支の由来」でした~
これは、あっという間に終わる(^∀^●)