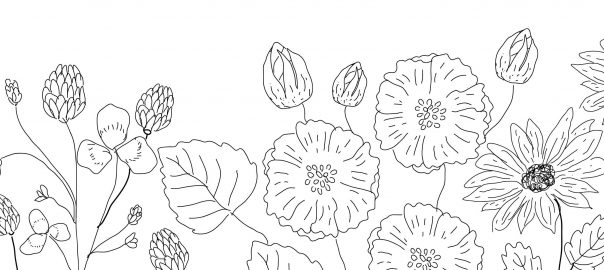古い雑誌を取り寄せました。
『季刊民話』民話と文学の会
その創刊号で、1974年12月1日発行。
全96ページの薄っぺらな冊子です。
編集後記に、創刊号を作るために、奥丹後、会津、出羽とよく旅をしたと書かれています。民話の雑誌は足でかせいで作らねばならないとも。
その旅で見つけた語り手は、その土地でおそらく一生を終える人たち。その語りは、その土地の言葉で、その土地独自の物語。
生成AIで動画まで作れる時代に、このような雑誌が保存され市民の目に提供されるとは、ほんに、図書館は宝箱だと思う。
この雑誌に掲載されている話のいくつかは、これから再話して語ってみようと思いますが、今回は、松戸市にある幼稚園の先生のエッセイについて書きます。
「おむすびとパンツ」という題の文章です。
先生はいつも園の子どもたちに昔話を語っているようです。
あるとき、「おむすびころりん」を語りました。
「むかし、あるところにおじいさんとおばあさんが・・・」と語り始めると、子どもが、「知ってる!桃太郎だ」といいました。
これって、今でもよく経験しますね。ヤンなんかしょっちゅうです(笑)
そのとき、先生は、なにくわぬ顔で先を続けました。すると、子どもが首をかしげます。先生は、「始まりは桃太郎と似ているけれど、違う話だよ」と説明を入れます。
ね、説明を入れるんですよ!
おじいさんは、おむすびをひとつずつねずみの穴に入れていきます。ぜんぶ入れ終わったとき、先生は子どもたちに相談するんですって!
「もう何もいれるものがなくなった」って。すると子どもが、
「まだあるよ、パンツが残っている」
先生は、
「パンツもころりんすっとんとん」と語る。そして、「あーあ、もうなんにもない」というと、子どもが、
「あるよ、おじいさん入っちゃいな」
先生は、
「それじゃあ、目をつむって、えい!おじいさんは、穴の中に飛びこみました」
そうやってストーリーは、あるべき道を進んで行くのです。
この先生は、子どもの反応を見ながら、手ぬぐいや着物などを穴の中に投げこんでいくそうです。子どもと語り手とが一体となって話をつくりあげていく。
この場面が、子どもたちがいちばん熱中して聞き入って来るそうです。
うーん、まいった!
子どもと一体になる語りは、ヤンも目指しているけれど、その方法はとっても難しくて、いつも試行錯誤。
まずはテキストに書かれた言葉にとらわれずに、話の魂を理解して自分の心に取り込むこと。そこではじめて言葉は自在に働くし、聞き手の気持ちと一体になれる、と思う。
先生は、子どもにとって民話だけがすべてではないとしながらも、こういいます。
「わたしが話している昔話を子どもたちが大きくなったその日に、自分の子どもたちに語って聞かせてやれる日があればと思いつつ、ひとつでも多くの昔話を自分のものとして知り、子どもに面白く語れる人になりたいと願っています」
がんばります。
すてきな先達に会えました!

子どもの柴刈りの写真(季刊民話)
**************
昨日はおはなしひろばを更新。
「おおかみサラマル」聞いてくださいね~
さてさて、毎日バタバタしていて既読スルーしていた井戸端会議のみなさんの記事をじっくり読み返さなくては~