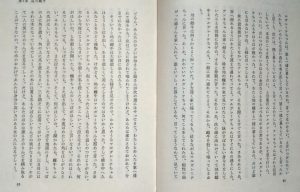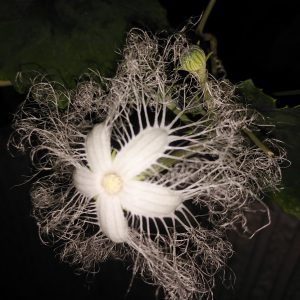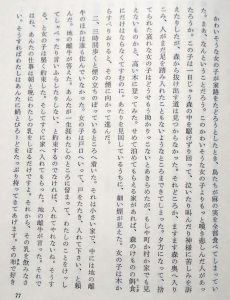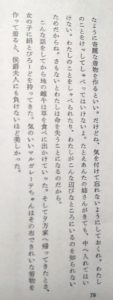マックス・リュティ『昔話の本質』報告
第5章生きている人形ー伝説と昔話
グリム兄弟が『子どもと家庭のための昔話』を出版したのは、1812年でしたね。
そのあとじきに、『ドイツの伝説』を出版しました。1816年・1818年。
これ以降、世界じゅうで昔話と伝説が集められ、出版され、研究されるようになりました。これは、グリム兄弟の偉大な功績のひとつです。
そして、それは、世界の人びとにどんな影響を与えたのでしょう。
グリムの時代は、識字率が高くなり、口伝えがどんどんなくなっていって、本来の昔話の伝達方法(メディア)が衰退する時代、その中でのグリム童話の出版です。
リュティさんは、昔話が世代から世代へ口伝えにされることは、今日では、破壊されたに等しいといいます。
いまは、新聞雑誌、ラジオテレビの時代だからです。
あらまあ、それどころか、リュティさんより数十年後の私たちの時代は、ネットの時代ですね。本もネットで読める。
今はこんな時代ですが、グリムに始まる昔話集・伝説集の出版によって、昔話・伝説はよみがえっただろうか。と、リュティさんは問いかけます。
答えは、青少年にとっては、よみがえったといえると言っています。
口伝えがなくなったその隙間を埋めているのが、昔話集と伝説集だというのです。
親や教師が、子どもたちに昔話をするとき、本に書いてあるとおりに語ったり、読んだりする。そのための昔話集なのです。
大人が子どもに読む、子どもは聞く。
そして、グリム童話は、世界じゅうで最も人気の高い昔話集なのです。
(みなさん、語りの森昔話集も、子どもたちに読んだり語ったりしてくださいね~)
伝説は、地域的な要素が大きいです。
昔話よりはるかに強く語り手と聞き手の置かれている環境と結びついている。
だからこそ、子どもは、真実性のある話として、伝説に夢中になるというのです。
子どもは伝説を読む。幼いころ夢中で昔話を聞いたように。
かつて『子どもと家庭のための奈良の民話』を再話編集した時、かなり多くの伝説を入れました。語り手も聞き手も、自分の土地の話として愛情を感じることができると思います。奈良の子どもたちに読んでほしいと思います。
おっと、話を戻します。
昔話や伝説を本にするというのは、子どもたちにとって大きな意味がある。
わたしたち、語り手はこのこと、よくわかりますね。
では、大人にとってはどうか。
リュティさんは、大人は昔話は子どものものだと考ているし、伝説も衰えているといいます。
なんか、どうしようもないみたいです。悲観的ですね~
でもわたしはね、大人のわたしはね、昔話を読んでると、励まされるのです。
がんばろ~と思えるのです。
小説だって面白いし夢中になるし考えさせられるけど、昔話はストレートにダイレクトに、励ましてくれるのです。
みなさん、そんなことありません?
わたしが子どもっぽいのかなあ。
おっと、話を戻します。
ともあれ昔話と伝説は、数百年の間、語られ伝えられてきた。
昔話と伝説の違いを、具体的に見ていこうというのが、この章の目的です。
次回は、めっちゃ怖いアルプスの伝説を紹介します。
*********
きのうはzoomを使ったおはなし会でした。
楽しかったよ。
もちろん、語りが楽しかったの。
でも、zoomに入られへん、顔が写らへん、声が聞こえへんという騒ぎもおもしろかった。
ジェニィさんが報告してくださるので、お楽しみに~o(*^@^*)o