マックス・リュティ『昔話の本質』報告
第3章竜殺しー昔話の文体
竜殺しって、なんだか物騒な題名ですね(笑)
ここでは、いわゆる竜退治の昔話を一話取り上げて、昔話の文体について説明されています。
とりあげてあるのは、二人兄弟型昔話のスウェーデンの類話です。
ただし、この話の原典を翻訳で読むことはできません。部分的に引用されているので、それを載せていきますね。
二人兄弟型昔話は、きっとどこかで見たことがあると思います。
身近なところでは、グリム童話の「二人兄弟」。
めっちゃ面白くって、語りたいんだけど、めちゃめちゃ長いのです。
どうぞ、読んで見てくださいね~
はい、では、本題に入ります。
まずは、発端句についての説明です。
「むかしあった、いつかあるだろう。これがあらゆる昔話の発端である。『もし』もなければ、『ひょっとしたら』もない。鼎(かなえ)には確かに脚が三本ある。」
これは、ブルターニュ地方のある昔話の発端句です。(発端句についてはこちら⇒)
リュティ氏は、これを、昔あったことは将来もあるだろうという昔話のささやかな哲学といいます。
昔といってはいるけれど、じつは過去のこと、もう終わったことではなくて、これからも起こることなんだよといって、語り始めるのですね。
たしかに、人間同士の戦いも、洪水も、感染症も、昔あったことは必ず繰り返されます。確実に。
さらに。
「『もし』もなければ『ひょっとしたら』もない。鼎には確かに脚が三本ある」というのは、昔話が世界を描くときの確かさ、明白さを面白おかしく言い換えたものだと言います。
昔話の文体が、鮮やかで、描写が確かだというのです。
わたしたちは、《昔話の語法》やそれぞれのところで昔話の文体(表現)について学んでいますね。
復習もかねて、少しずつ読んでいきます。
まず、取り上げるスウェーデンの昔話(題名が書いてないのです、ごめんなさい(⓿_⓿))は、百年以上前に記録されたものだそうです。
ふたりの兄弟の名前は、「銀の白」と「小さい見張り」。
まず銀の白が旅に出ます。

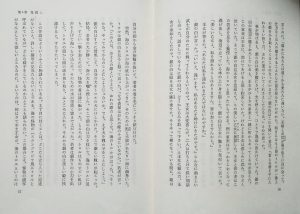
はい、説明は次回。
読んでおいてくださいね~(❤´艸`❤)






