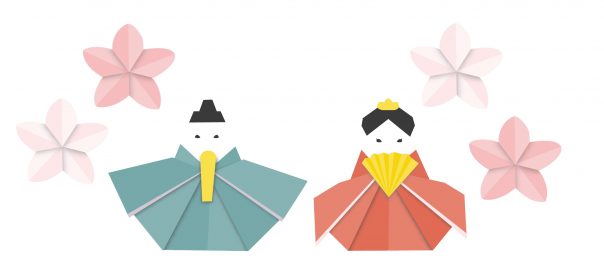急に暖かくなりました。
それはええけど、花粉も黄砂も飛んでます(っ °Д °;)っ
めげずにプライベートレッスンです~
「宗旦ギツネ」のテキスト整理
『京都府の民話』日本児童文学者協会/偕成社
京都市上京区に残る伝説です。
初めは再話ということでエントリーされたのですが、本文が結構きちんと再話されているので、手を入れて整理するだけで語れるだろうと判断して、テキスト整理のレッスンにしました。
が、やってみると、ラストのモティーフに合理性がなく、これでは語れないなと思いました。
でも、うまい具合に、フルーツさんが、宗旦ギツネの伝説そのものを調べてこられていて、ほかにさまざまな伝承があるのが分かりました。それで、そちらに置きかえて、整合性のある話にしました。だから、ラストは真っ向、再話になりました。
おもしろかったです。
それと、読み物としての文章になっているので、聞くとイメージが見えない部分がありました。その部分は整理しました。
読んでわかりやすいのと聞いて分かりやすいのとは違いますからね。
次回、もう一度テキストを語れる形にして完成させることになりました。
フルーツさん、貧乏神からきつねばなしへと、川の流れのよ~に~
楽しんではりますo(*^@^*)o
わたしも楽しい!
きつねといえば、4月の大人のためのおはなし会(15日)のテーマが「きつね」。
ウーカーさんの故郷の言葉で語るきつねの伝説もありますよ。
みなさん、聞きに来てくださいね~