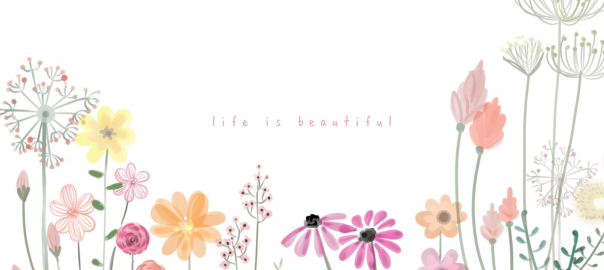5月20日(月)
こども園
4歳さん 1クラスずつ2回
ろうそくぱっ
おはなし「おいしいおかゆ」『おはなしのろうそく』東京子ども図書館
ろうそくぱっ
わたし「おかゆって知ってる?」
子ども「知ってる~」
子ども「知らん!」
子ども「赤ちゃんが食べるやつ!」
わたし「そうそう」
子ども「風邪ひいたときにな、食べる!」
わたし「そうそう!」
わたし「こんど、おうちで作ってもらいな!」
こんな感じでおかゆで盛り上がっといて、おはなしに入ります。
おかゆがどんどん広がっていくのが、ふしぎで、うれしそうに笑いながら聞いてくれましたよ。
わたし「はい、おしまい」
子ども「はや~い」
子ども「もっとゆっくりの!」
ゆっくり?早口やったかな?って、反省しかけて、はっと気がついた(笑)
わたし「こんどはもっと長いのするね」
子ども「うん!!!」
子どもって、どんどん言葉を覚えていくんやね~
5歳さん 1クラス
ろうそくぱっ
おはなし「半分のにわとり」『語りの森昔話集1おんちょろちょろ』
絵本『まるさんかくぞう』及川賢治・竹内繭子/文溪堂
ろうそくぱっ
「にわとりを半分に分けてしまいました」っていったら、全員があんぐり口あけて目を真ん丸にして見つめてきたので、おかしくて~
思わず、「そこまで、大丈夫?」って聞いてしまった(笑)
わたし「つまりね、ふたりの女の人は、それぞれ半分のにわとりを飼うことにしたのです」
子ども「死なへんかったん?」
わたし「死なへんかってん」
子ども「すご」
「半分のにわとり」は、聞き手にかなり想像力を要求するので、今まで幼稚園ではやってなかったのです。
今回思い切ってやってみたら、なんのなんの、ちゃんと想像してびっくりしながら、最後までついてきてくれました!
5月の若葉のような、言葉と想像力の芽吹きが、楽しく頼もしく思えた、語り手に取って幸せなおはなし会でしたo(*^@^*)o