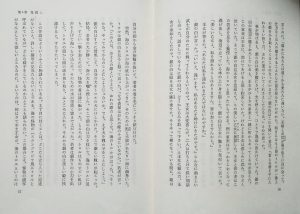マックス・リュティ『昔話の本質』報告
第3章竜殺しー昔話の文体
前回(一昨日)の井戸端会議の最後に写真で載せておいた竜退治のおはなし、読みましたか?
もしまだなら、先に読んでから、今日のところを読んでね。
きょうは、そのおはなしの文体の特徴について、リュティさんが解説している所をまとめます。
なんか、ぎゅう詰めに説明してはる(笑)
分けて書きますね
話の筋は目標に向かってまっすぐに進む
総括すると文体の特徴はそれに尽きるということです。
おはなしを読んで、多分皆さん感じたと思うんだけど、「これって、あらすじ?」って、疑問に思わなかった?
私は思った。
でも、あらすじじゃなくて、これが原話そのままなんだって。
じゃあ、まっすぐに進むという特徴を詳しく見ていきます。
風景や外観を細かく描くことはしない
例えば、トロル。
どんな外見か、いっさい説明がない。ひとこと、「怪物」っていうだけ。
昔話にはこれで十分なんだって。
例えば、海辺。
事件現場なのに、どんなところなのかいっさい描写がない。
トロルが出てくるときに、「泡と大波があたり一面に渦巻いた」というだけ。
それに対して多くの創作童話では、例えば主人公の入っていく街の様子をいかに詳しく丁寧に描いていることか。狭い横町、美しい街角、切妻屋根の家・・・
ほんとうの昔話には、そういうものは何一つ出てこない。
ただ、銀の白の入っていく町では、「家という家が黒い幕をかけて」いますね。
これは、描写ですね。
でも、これを描写するのは、ストーリーに関係があるからなんです。
だって、銀の白は、変だなと思って町の人に聞くでしょ。そしたら、トロルがお姫さまをさらいに来るってことがわかる。だから銀の白は、トロルをやっつけに行く。そのための「黒い幕」なんです。
たまにグリムが、魔女の長い曲がった鼻とか赤い目について書いているけど、それは、グリムさんが後から付け足したもの。
ほんとうの昔話は、年とった魔女とか、醜い老婆としか言わない。
これを、リュティさんは、「描写力の欠如」といって、それが、昔話が面白い理由なんだといっています。
昔話の主人公は、旅をし、行動する
立ち止まったり、驚いたり、観察したり、思い悩んだりしないって。
たしかに、銀の白はそうですね。うだうだ考えていないですね。
登場人物の心の中についても描写しないのです。
感情や関係は外部へ投影される
例えば、しらみとり。
銀の白は、いきなりおひめさまに頭のしらみを取ってもらいますね。
おかしくない?
わたし、いつも、この類話を読むとき、この場面で笑ってしまう。
しらみかい!って。
リュティさんの説明、おもしろいから長めに引用しますね。
しらみをとることは原始民族にはたいへん好まれた欠かせない仕事であったとか、しらみとりは、婚約の儀式になることもあったとか、しらみをとる女は取ったしらみを食べるのが常で、そうすることによってしらみを取られた男の血を体へ受け入れた、
などと知っている必要は全くない。
(≧∀≦)ゞ(≧∀≦)ゞ(≧∀≦)ゞ
だからね、しらみ取ってるってとこで、ああふたりは深い関係になったんやなって思ったらよろしい、ということなのよ。
ほら、あとで、トロルに「この人は、~おれの姫だと思うな」って言ってるでしょ。
例えば、指輪。
お姫さまが銀の白の髪の毛に指輪を結びつける。これは?
そう、信頼と愛情を感じ取ればいいのね。
人物の孤立化
二人兄弟は別れて、ひとりで行動します。
お姫さまはお供を連れてひとりで海辺へやってくる。
お供が逃げるから、お姫さまは完全にひとりになる。
主人公とお姫さまは、二人きりで向き合うことになる。
孤立した者同士が一対一。
しかも、このふたり、それぞれに独特な存在です。
銀の白は、母親がリンゴを食べて妊娠した、その子どもなんだって。
お姫さまは、王の娘ということで際立った存在ですね。
昔話は、社会の末端にあるものを主人公にするっていうのは、常識ですね。
くっきりした極端なものを好む
昔話が、金・銀・鉄・水晶を好むのは、それらが、キラキラ輝くからだけではないし、貴重なもの(極端なもの)だからというだけでもない。昔話は、硬い物、形のはっきりしたものを好むからなのです。
それでね、昔話を聞く人は、くっきりした確かな明るい語り口から、昔話にそなわっている明るい輝きを自分の中に取り込むことになるんだって。
なるほど、それで昔話は楽しいんだヾ(≧▽≦*)o
はい、きょうはここまで。
*************
オンライン講座日常語の語り入門はしめきりました。
あちゃ、しまった~って思ったかた、一人ぐらい何とかなりますので、どうぞ~