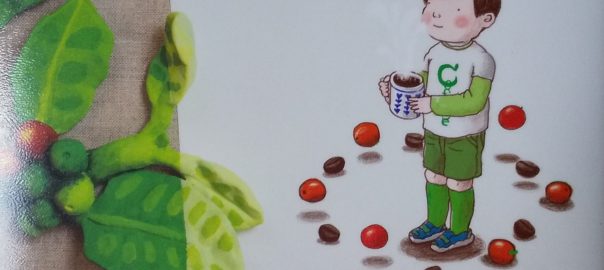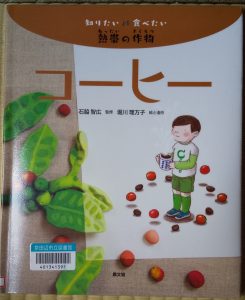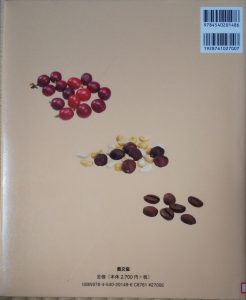4月を最後に対面では出来ていなかった初級クラス、にんまり再開しました。
1.とらとほしがき 『語りの森昔話集2/ねむりねっこ』語りの森
1番で語るのは気が楽ですね!その後、私はみなさんの語りをまったり聞くことができました。そして、語りについて…とらのユーモアなところを楽しむ語りになったらいいなという事が一つ。後半に入るところで、どろぼうが牛をねらって忍び込んでいる、とらが牛小屋に入っていくと、どろぼうは牛と間違えてとらのせなかにとびのる、この場面を聞き手がイメージできるように意識して語った。
ヤンさん…とらが子どもをさらっていくのは諦めて、牛をおそうことにしたところを、そのように語りの雰囲気を変える。その上で、しっかりイメージして語れば聞き手に伝わる。とのことでした。
2.仁王さまと夜遊び 語りの森HP
個人レッスンで一度ヤンさんに聞いてもらったはなし。その時は、おばあさんがおならをした後「におうか?」と聞いて仁王さまが「仁王か」というが、洒落だとすぐに分からないかもしれないと思い、この度テキストをいじってみた。「におうか、仁王か」…とイントネーションを変えて2回言う事をこの場で試してみたとのことでした。
ヤンさん…聞き手の子どもがその時分っても良い、後で分かっても良い。わかったか?今のしゃれやで!と言ってもいい。聞き手への理解の程度(全体のどのくらい)は語り手が決めて良い。ちょっと全体的に語りが上品だったかな、最初ないしょ話のようにしていたのはなんで?
語り手さん…『おもしろいはなしやで』という雰囲気の自分の語りを抑えて、聞き手に任せるようにした。
ヤンさん…そういう事なら、おばあさんのおならから雰囲気を変えて語って、はじける意外性で笑わせるような、ねらった語り方でも良い。それでも語りは、色を付けずに語る練習をして、子どもの前に出して、子どもの反応で語りが決まるもの。子どもへの問いかけで定着する間がある。
3.なぞの歌 『日本の昔話2/したきりすずめ』おざわとしお再話
歌が語りづらい。心情に訴えかけるような、若い二人が恋に落ちるストーリー構成になっている。そんな中で度々出てくる歌『恋しくば、たずねきてみよ十七の国。くさらぬ橋のたもとにて、夏鳴く虫のぼたもち』この大事なポイントとなる歌を、言い方を変化させて語ろうと思った。
ヤンさん…歌が大事になるので、考えたりせずに、さらっと語る。特に一番最初は、ゆっくり和歌らしくなめらかに語る。聞き手に、なんやろか?と思わせるようにする。また、若者が座頭さんに尋ねた時の、座頭さんのセリフとしての歌は聞き手に説明するように、はっきり相手に伝わるように語る。
4.犬とねことうろこ玉『子どもに語る昔話1』こぐま社
語りを聞いた時におもしろいなと思って覚えた。長らく初級クラスを休んでいたが、また参加できるようになり勉強したい。
ヤンさん…以前の語りとは違って、言葉の切れ目はなくなっていたと思う。自分の癖は自分で聞くと分かるので録音して聞いてみるのも良い。一方で、なめらかになりすぎていて、起伏がない気がした。聞き手に聞かせるのに、おもしろいところ、山場をつかんで語る。この場合は前半・後半と二つの山場があり、後半の山の方が高い。なので、この山の頂上に向かって語っていく。また、テキストの一文一文のおもしろさに違いがあるので、自分の心も動かしながら聞き手が興味を持つように語る。ここが大事!というところを意識して語る。小さなおもしろいところは聞き手が見つけてくれる。
しっかりした長い話は、『テキストが求める間』で語る。また、長い話は、自分の解釈に自信を持ちがちになるので、どう~?という聞き手への問いかけのように語る。
5.白雪姫『語るためのグリム童話3』小峰書店
時間があったので、ジミーさんがリクエストに応えて語ってくれました。
ヤンさんの語り カメの笛『ブラジルのむかしばなし1』カメの笛の会編 東京子ども図書館 手遊び どんぐりころちゃん
ノート式おはなし講座 語りこの愉しい瞬間p36
語り手が仕掛ける間…聞き手が求める間をつかむことが大事であって、子どもとの関係性も出来ていないといけません。子どもの目を見て、分かっているな、分かっていないな、ということが、語りながら分かるようになるので、どの程度の理解で済ますかは自分で決めて、その自然にできるポーズが間となります。敢えて間をおいて仕掛ける事もできます。
笑い話の語り方…笑い話も怖い話も間がすべてです。ヤンさんの『ホットケーキ』失敗談では、笑わせようと意識しすぎて、イメージを伝えきれなかったそうです。笑わせたい気持ちを優先したために、聞き手が返してくる間を待って返せなかったとの事です。イメージを伝えることを基本に置いたうえで、聞き手の返してくる息づかいを落ち着いて読み取り、聞き手の求めているものに誠実に返せば、間が生まれます。
『間』については、初級クラスには早いかな~とヤンさんは言われていましたが、知っておいた上で、実践に臨めるのはありがたいですね。失敗したり、なんかうまくいったりした理由が、その場で理解できる訳ですから、納得して次に向けて練習できます。うーん、聞き手とのやりとりができるようになったら、本当の「語り」ですね。おはなしを覚えてイメージを伝えて、最後まで行くことがなんとかできる段階では、おはなしの醍醐味に到達してないわけですね。難しい!ノート式タイトルにもあるように 語りこの愉しい瞬間 に向かって進んでいきたいです。
この度も盛り沢山な内容で、おなかいっぱいになりました。そして、初級講座が行われていなかった間に、自主トレ会の開催や、zoom活用などのおかげで、気持ちが途切れることなく、この10月再開に繋げる事が出来たように思います。心を寄せて行動してくれるヤンさんやみなさんに感謝です。その自主トレ会が新たな形となり「中級・初級クラス合同の語りの場」となって定期的に行われる運びとなりました。クラスの垣根を越えてのおはなし会・交流の場となります。楽しみです。
次回、初級講座11/9(火)