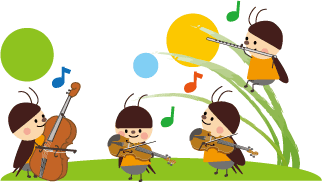すっかり秋らしくなりましたね。
暑くなく寒くなく、過ごしやすい…と思っていたらたまに暑い日もあって「また夏?!」と汗だくになって買い物に行ったり…
今月のプライベートレッスンの報告です(^^♪
1日目
語り「ねこのしっぽ」『語りの森昔話集4おもちホイコラショ』語りの森
「ありとこおろぎ」『語りの森昔話集1おんちょろちょろ』語りの森
2日目
日常語の語り「うりひめの話」『語りの森昔話集2ねむりねっこ』語りの森
日常語のテキスト「仁王さまの夜遊び」語りの森HP → こちら
3日目
テキスト選び勉強会
今回は初めての内容があります。
〝テキスト選び勉強会〟です。
これは、プライベートレッスンを申し込まれたかたが、たまたま選ばれたテキストが語りに向かないねという話になり、急きょ、ではどこがどういう理由でむかないのかを教えてもらう勉強会になったわけです。
おはなしを覚える時のテキストというのは、特に語ることを意識して編集されている物は少ないので、有名な児童書の中から選ぶことも多いですね。
聞き手が分かるならば問題ないわけですからそのまま覚えるのも一つの手です。
しかしながら、語っているときに聞き手が理解していないと感じることがありませんか?
すてきな話だから選んだのに、聞いていて分かりにくいのはなんでなんでしょうか?
そんな疑問に答えてくれる勉強会が今回の〝テキスト選び勉強会〟でした。
ある有名な外国の昔話を集めた本の中から1話を選んで、話の最初から順を追って説明していただきました。
1行ずつ説明していただいたのですが細かいことは書ききれないので端的に言いますと、語るために再話・編集された本の話が一本道を突き進むがごとくストーリーだけを追って真っすぐ話が前に進むのに比べて、読み物として編集された本の話は、寄り道や脇芽が多くてそちらにもイメージをむけなくてはならず、それはストーリーとは関係ないので結局混乱するだけで、結果として分かりにくいこととなるわけです。
寄り道や脇芽というのは、よくないものというわけではありません。
それは例えば、あることの理由を後になって説明するからなぜそうするのかがよく分からないまましばらく聞いていなくてはならないとか、時間が逆流しているとか、たくさんの形容詞や修飾語とか、翻訳者の特徴的な美しい文体とか、翻訳調とか、説明過多とか、同じ出来事を違う言葉で描写しているなどです。
これらは、読んでいると全く違和感がなくてむしろこれらがあるから読んでいて楽しく美しいと思えるところです。
わたしもこの話は大好きになりました。
でも、翻訳されたかたの美しい文章が完璧すぎて、少々単語を入れかえたりするだけでは耳で聞いて分かりやすくするのは無理であると今回分かりました。
ですから、方法としては自分の聞き手さんたちが分かるならば、このままを覚えるのがひとつ。
それと、今回のようにこのテキストはあきらめて他の話を探すほうに力を入れるか…。
テキストを選ぶというのは、それで聞き手へ伝わるかどうかが決まるのでここをクリアすれば勝ったも同然(笑)という大事なことです。
それだからとても悩みます。
わたしが昔話の語法を勉強するのも再話の勉強をするのもすべてここにつながります。
今回は急に決まったのでヤンさんはたいへんだったと思いますが、他では聞けない内容だったし、本当に勉強になり、かつ楽しかったです。
また、他の既存のテキストを使っても、こんな勉強会があったらいいなと思いました(^_^)