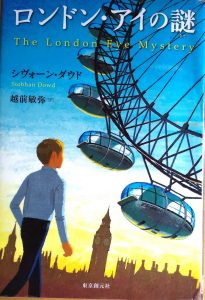ちょっと遅い記録です。
6月17日(月)
こども園
4歳 1クラスずつ2回
ろうそくぱっ
おはなし「ひなどりとねこ」『子どもに聞かせる世界の民話』矢崎源九郎/実業之日本社
ろうそくぱっ
毎年、どのクラスにも、おはなし会に慣れるまでに時間のかかる子がいます。
そして、慣れるまで独自に活動します。
その活動が、わたしに「話しかける」という子が一定数います。
わたしは、その子と「話をする」か「おはなしを進める」かで、引きさかれます。
このバランスを崩すと、おはなし会自体がくずれます。
なかなか悩ましい問題です。
5歳 1クラス
ろうそくぱっ
おはなし「ミアッカどん」『イギリスとアイルランドの昔話』石井桃子/福音館書店
絵本『そそそそ』たなかひかる/ポプラ社
ろうそくぱっ
5歳児になると、経験が積み重なって、それなりにおはなし会が成り立ちます。
のめりこむ子と、テキトーに付き合う子と。
そうなると、こっちのもんで、大きな渦を作ってひきこみます。
さて6月、ここからが勝負です。
秋~冬に向けて聞く耳が育っていけば、2月の最後のおはなし会で「ジャックと豆の木」が聞けます。
今年はどうでしょうか・・・
************
きのうの《おはなしひろば》はイスラエルの昔話「人に悪いことをしなければ自分にもされない」。考えさせられる話です。