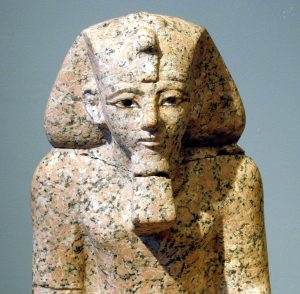冬の第九の練習が始まっている。
夏のカルミナ・ブラーナが、ヤンにはあまりにも過酷だったので、あ~、いつもの第九~、ルン
なんて、余裕していてはいけないのだ。
努力がなければ、声を合わせる喜びにたどり着けない。
☆☆☆
2017年12月10日(日)14時開演
京都コンサートホール・大ホール
指揮 角田鋼亮
管弦楽 京都市交響楽団
ソリスト S:石橋栄実 A:山田愛子 T 二塚直紀 B 三原剛
☆☆☆
スケジュール帳にチェック入れてくださいね~
が、しかし、その前に、まだ団員数が足りない。
入団テストなしでだれでも歌える合唱団。とっても丁寧な指導と、あたたかい先輩たち。
あなたもいっしょに歌いませんか?
練習日は、毎週金曜日、18:30~20:45
練習場所は京都市北文化会館(京都地下鉄北大路駅すぐ)や龍谷大学響都ホール(JR京都駅前)
団員募集締め切りは9月15日。
問合せ先:京都ミューズ ☎ 075-441-1567(平日11時~17時)
けど、暑いね~
毎日、気温が体温です。
体調管理、しっかりやろうね💖





1929-300x169.jpg)

 今日は立秋。
今日は立秋。