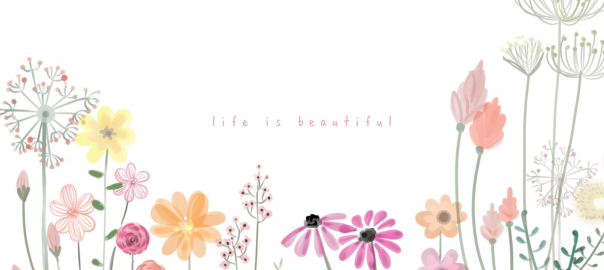相変わらず、梅雨の曇り空と雨のくりかえしで、からっと晴れた日が恋しいです。
6月25日、第28回語法勉強会「ヘンゼルとグレーテル」がありました。
資料としたテキストは、『語るためのグリム童話1』(小澤俊夫/編訳 小峰書店)です。
いつものように、昔話の語法の指摘をしてもらい、その後にこのテキストとグリム童話の2版と7版のテキストとで、三種類のテキストの比較の結果を説明してもらいました。
「ヘンゼルとグレーテル」の話は、創作を思わせる、つまり昔話的でない個所があるので、テキストの比較をしてそれらを丁寧にみていくという作業をしたもらったわけです。
翻訳されているグリム童話の2版は『完訳グリム童話Ⅰ』(小澤俊夫/訳 ぎょうせい)です。
7版はいろいろの訳が出ています。
グリム童話は、エーレンベルク稿から7版まで、グリムさんが版を重ねるごとに手を加えておられるので、「ヘンゼルとグレーテル」も2版より7版がだいぶ長くなっているのがよくわかりました。
どの部分を長くしているのか、家に帰ってから改めて2版を読んでみると、短いぶん2版はやっぱり簡潔です。
主人公の幸せに向かって、始めから終わりまで一直線に進むために昔話の語法があると思います。
そこが、創作の物語と大きく違うところです。
個人的には、「ヘンゼルとグレーテル」は、前半のふたりが親に捨てられるところの説明が話の筋になっているので長く、どういう風に明るく語ってみても悲しいので(笑)、覚えるのには二の足を踏んでいました。
でも、お菓子の家という夢のようなアイテムもあるし、女の子の成長の話としてはいい話だと思います。
好みの問題でしょうが、わたしは2版のほうが耳で聞くのにわかりやすいし、かわいそう感が少ないと感じました。
ただし、そのままではわたしは語れませんから、振り出しに戻る状態になってしまいますが。
今回の勉強会は、語法の勉強に加えて、テキストの版の比較をしてもらって新たに分かったことがありました。
わたしは、グリム童話を覚えるときは他を当らずに『語るためのグリム童話』一択だったのでしたが、「ちょっと待てよ~、ほかの版も比較したほうがいいよ~、早まるなよ~」と言ってもらったことで、教訓になりました。
グリム童話は大好きなので、これからはテキストを決めるまで慎重に比較してから覚える段階に進みたいと思いました。
テキストを決めるときや再話を勉強しているときに思うのですが、何か探し物をしているのと似ています。
今日も、探し物があって天上収納に入ったのですが探し物はなく、関連するものは出てきたけれど使えずすてることにし、となりにあった物が全く別物ですが別の用途で使えるから持って降りたということがありました。
で、探していたものはないので買うことになるのですが、ごちゃごちゃの天上収納に上がって探さないとこの要件は完結しないというのが、テキスト決めや再話に似ていると思います。
わたしだけですかね?
どうもすいません<m(__)m>
今回も梅雨の湿気を忘れさせてくれるような、楽しい勉強会でした(^O^)/