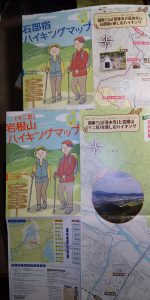先週火曜にありました、初級クラスの報告です。いつもすぐに7話のエントリーが埋まってしまうのですが、今回は珍しく少なかったので、ジミーさんも語ってくださいました!
(手遊び)
弁慶が五条の大橋渡るとき うんとこどっこいしょ うんとこどっこいしょ うんとこどっこいしょと 言て渡る♬
学校のおはなし会は子ども達とも顔なじみになっているのでいいのですが、図書館のおはなし会で初めて会う子どもがいる場合は、手遊びをして触れ合ってからのほうが語りやすいと感じます。
(語り)
①妖精の丘が燃えている 『子どもに語るアイルランドの昔話』/こぐま社
このおはなしを選んだ理由は、アイルランドに旅行をした友達から写真を見せてもらったからだそうです。アイルランドはイギリスの左側にある島ですね、北海道ぐらいの大きさですが、日本人にはあまり馴染みがありませんよね。でも、写真を見てイメージができたのか、情景が見えた素敵な語りでした。
また、このおはなしは死んだおっかさんの知恵もかりて、妖精たちを追い出すことに成功します。いくつになってもお母さんの有難みを感じることがあり、このおはなしに決めたそうです。
最後の段落に「こんなおそろしい目にあってから、ブラスケットのおかみさんは、昼であろうと、夜であるうと、・・・」とあるのですが、ブラスケットという言葉が抜けてしまいました。しかし、最初に1度できてきただけであり、子ども達も何のこと?と疑問に思われても困るので、省いていいそうです。
②くもと夢 『語りの森HP』/語りの森
ジェニィが語りました。「夢の蜂」の類話ですが、人の魂が寝ている間に昆虫になって抜け出すのではなく、このおはなしは外(泉水)からくもができてきて、男の鼻のあなに入っていき、宝のありかを教えます。また、最後は宝を均等に分け合い、2人とも幸せになる点が気に入りました。
1年生から6年生がいる場でのおはなし会で語る予定にしているので、難しい言葉は説明する必要があります。
①荒れた長者屋敷あと → 人が住まなくなった、お金持ちの家
②泉水 → 池 ③千両箱 → 小判(お金)のたくさん入った箱
子ども達に辞書に書かれた言葉の意味を言うのではなく、おはなしがイメージできるよう、子どもに分かる言葉で説明することが大切だそうです。
語りの森HPには標準語のテキストが掲載されていますが、『子どもと家庭のための奈良の民話1』にはヤンさんの日常語で書かれています。
③捨て子と鬼 『日本の昔話4」』/福音館書店
内容を理解してもらおうとゆっくり語るのではなく、ストーリーに重きをおいて語ることを意識されたそうです。
ゆっくり丁寧に語れば子ども達に分かってもらえるか?「そうではなく、むしろ間をあけずに語るほうがよい」とヤンさんより。この初級クラスでは何度も指摘されていますが、句読点できると、聞き手は分かりづらいのです。
細かな点では、
(P49)「それみろ。ぐずぐずしているから、鬼がかえってきちまったじゃないか。さあ、はやくこの中にはいれ」といって、三人を押し入れの中にかくしてくれました。すぐに鬼が裏口からはいってきて、鼻をフスフスさせ・・・
押し入れの中にかくしてくれました。の後に間を取り、子ども達にこれからどうなるか?を考えさせる間を取るといいそうです。
同じように、(P50)道ばたにすわってやすんでいるうちに、ついぐうぐうねむりこんでしまいました。の後にも間を取るといいでしょう。
④酋長カイレ 『語りの森昔話集2』/語りの森
中学生の、特に男の子にがよく聞くそうです。語るときに技巧は必要なく、普通に語るだけでストーリーを楽しめるおはなしです。
先月のブログにも書かせてもらいましたが、Uさんは練習しすぎる傾向にあるそうで、今回の練習期間は約2週間、言葉を頭に入れた状態での発表でした。それが理由なのか、句読点で切れてしましました。例えば最初の一文「若い酋長のカイレは、川のほとりの小さな村に、妻とふたりで住んでいました」とありますが、間をあけずに一気に語りましょう。語ってから、少し間をとり、聞き手に状況を飲み込ませるといいそうです。
⑤三枚のお札 『語りの森昔話集2』/語りの森
ジミーさんの日常語の語りでした。小僧さんが鬼ばばに追いかけられながらお寺に帰りつき、和尚さんが言った言葉 「こまったことだ。どこにかくそう。しょうがない、井戸の天井にかくれていろ」をどのように語ればいいか悩まれたそうです。和尚さんは鬼ばばが出ることは分かっていたから、落ち着いて語ればいいのか、それとも和尚さんも小僧さんと同じ気持ちで、急がなければ鬼ばばがやってきてしまう、と焦っているのか?
重要なことは、子ども達は和尚さんではなく、小僧さんになって聞いている、「急がないと鬼ばばにつかまってしまう」という気持ちということです。ですので、ゆったり語ると聞き手は「早くして~」という気持ちになるのでいいのでしょう、とのアドバイスでした。
≪ヤンさんの語り≫
ちいちゃいちいちゃい 『イギリスとアイルランドの昔話』/福音館書店
聞き手によって語り方が変わってくるおはなしだと思います。おはなしの内容は知っていますが、最後はどんな風にくるのか?とドキドキしながら聞いていました。分かっているのに、面白くて怖かったです!
この後、ノート式~の「おはなしの覚え方」を勉強しました。詳しくはジミーさんの16日のブログ「入門講座3回目」をご参考ください。(手を抜いてスミマセン・・・(*_*; 苦笑)重要なことは最初のイメージを創るときから、大きな声で読む、覚えるときもしっかり声に出すことです。
以前、ヤンさんがどうしても覚えられないといっている人がおり、どのように覚えているかを聞いたところ、声に出していなかったそうです。
2019年度の勉強会もあと1回です。(1年が早い~!)