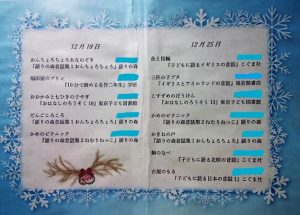ここ山城南部は、おだやかに晴れわたった元日を迎えました。
どうか、今年は天も地も、しずかにおだやかに、わたしたちに恵みを与えてくれますように。
若いころから、年頭に「今年のキーワード」を決める習慣があったんですけどね。
何年か前から「伝える」で動かないのですよ。
今年も、考えに考えた末、やっぱりこれしかないなあ、と言う感じで、「伝える」
去年、初めて孫(3歳)にお話を語ったのね。
・・・孫とは年に1~2回しか会わないんだけど、秋に帰省したときのこと。
娘がいうには、「「かしこいモリー」を語ってやったら、固まってしまってなだめるのに大変だった」って。
娘自身は5歳の頃、毎晩「かしこいモリー」を聞いてたの。その頃の彼女にとって必要なお話った。
けどね、お話は成長過程を見て選べ(笑)
こらあかんと思ったので、
おやつを食べてるとき、
わたし「おはなししてあげようか?」
まご「ん」
わたし「むかし、あるところに、ひなどりがお母さん鳥といっしょにすんでいました」
まご「・・・」
・・・・・・・
わたし「・・・とても得意そうに出てきましたよ。おしまい」
まご「もっかい!」
娘・じいちゃん・おじちゃん「おおお~!」
みんなさりげなく聞き耳を立てていたようで(笑)
昔々のお茶の間再現。いろり端再現。
子どもが独立してからは、地域の子どもたちに、ひとりでも多く、ひとつでも多く、昔話を伝えたいと思ってやってきたけどね。
ここへきて、わたしから聞いた話を、娘がわが子に伝えようとしたことにめちゃくちゃ感動。
そして、ばあちゃんが孫に語るという、古来からのすがたを再現できたことに感動。
わたしは、たまたま、子どもが生まれて、孫ができた。
幸運に感謝している。
わたしの持っているものを「伝え」ない手はない。
キーワード「伝える」のもつ意味も、毎年少しずつ深まっていきます。
みなさまの今年のキーワードは何ですか?
ひとりひとり、わずかな歩幅しかないけれども、まず一歩、進まなければ旅は続かない。
子どもは未来。
でも、わたしたちも未来を作っていけるよ。
今年もよろしくお願いします。