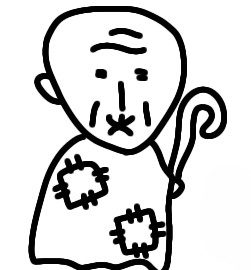12月も中ごろに入って、いよいよクリスマスの雰囲気が増してきてますね。
図書館に入ると、大きなクリスマスツリーが飾ってあります。
入り口を入ってすぐのコーナーはクリスマスに関する本がずら~っと並べられていて、にぎやかで華やかな気分になります。
そして、12月13日の図書館のお話会は、クリスマスの手遊びから始まりました。
参加人数は、子ども15にん、大人12にん。
たくさんの人が来てくれました。
手遊び メリークリスマス
おはなし 「ホットケーキ」『おはなしのろうそく18』東京子ども図書館
絵本 『ゆうぐれ』ユリ シュルヴィッツ/作 さくまゆみこ/訳 あすなろ書房
〃 『バスでおでかけ』間瀬なおかた/作 絵 ひさかたチャイルド
〃 『よくみると…さらに!』shimizu/作 絵 Gakken
手遊び さよならあんころもち
「ホットケーキ」は受けるのが当たり前の話だそうで、以前ヤンさんは、受けすぎて収拾がつかなくなるのでやるのを控えていた時期があると言ってましたよね。
そういえばおはなしのお部屋で語られたときにみんながひっくり返っていたのを思いだします(笑)
この日、常連も初めての子もいる中、いちいち大きく反応する受けすぎの子ども、もう知っていると次の内容を口にする子ども、とちゅうで何かの本を読みだす子どもと、そんな中でヤンさんがそれらのどれにも相手をしながら最後まで語るという姿を見て勉強させていただきました!
「ホットケーキ」はわたしも語ったことがありまして、昨日のあったかペーチカの会でも皆さんが鉄板だと言っていた通り子どもたちは喜んでくれます。
でも、わたしは、テキストのダジャレがいまいち気に入らなくて、そんなわたしなのでずっと語っていません。
語り手が納得していないのに語ってはいけないと思って、それならもっとほかの話を覚えたほうがいいと思いまして…。
でも、ヤンさんの「ホットケーキ」を子どもたちが喜んでいる姿を見ると、子どもが喜ぶ話をしないといけないなとも思います。
とか、あとでいろいろ考えていましたが、お話会はおはなしも絵本もとっても楽しくて、聞き手としてはいつものように楽しく満足してすごせたのでした(*^_^*)
でも、子どもたちが多くて、最後の絵本はヤンさんが子どもたちにガッチリ囲まれてしまって、たいへんでした。
ヤンさん、体力を使う回でしたね、お疲れさまでしたm(__)m