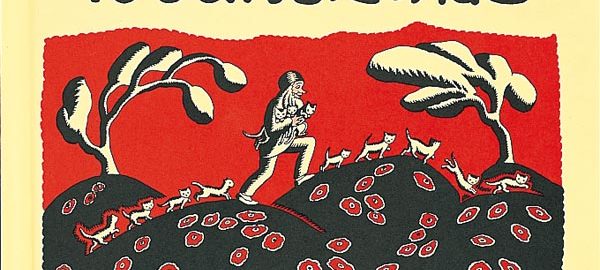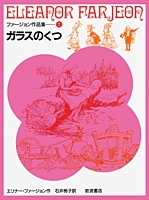『瀬田貞二 子どもの本評論集 児童文学論 上』報告
**********
第4章昔話《昔話ノート》
「昔話と児童文学―イギリスの場合」=昔話の再創造 1971年発表
昨日のつづきです。
昔話が幼い子のための文学として再話され、定着していったその時代の流れを、昨日は勉強しました。
今日は、昔話を種にして自分の文学を創作した作家たちについてです。
題材が昔話というだけなので、再話ではなく創作。その具体例。
ウォルター・デ・ラ・メア『再話集』1927年
「シンデレラ」「ねむりひめ」など19話。
デ・ラ・メアは、『ムルガーのはるかな旅』の作者ですね。
彼の短編は、伝承を元にしたものが多いそうです。
『再話集』の翻訳があるのかないのか、いくつか候補はあるのですが、今調べる方法がなくって
『かしこいモリー』エロール・ル・カイン 絵・中川千尋訳/ほるぷ出版 2009年
これも『再話集』に入っているんでしょうか?

エリナ―・ファージョン
『ガラスのくつ』1955年=「シンデレラ」を下敷きに(岩波書店刊で読めます)
『銀色のしぎ』1953年=「トム・ティット・トット」を下敷きに
昔話を下敷きに、「自由な登場人物をつけ加え、ストーリーを上積みして、はなやかなオペレッタのように仕上げた作品」
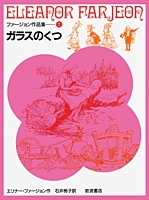
木下順二(1914-2006)
戯曲「夕鶴」
『わらしべ長者』1962年
『夢見小僧』1966年
瀬田先生は、これらの話を「再話」とすべきではないと言います。「テーマとナレーション(文体)が昔話のものとちがう」からです。
ヤンの考え・・・
デ・ラ・メアのは読んでないからわからないけど、ファージョンは、作品名に昔話の題名を使ってないのが、誠実だと思う。ちゃんと、創作だって表明してることになるから。けど、木下順二のは、ごまかしがあるような印象を与える。創作なのに、伝承かと思わせる。超有名人だから、罪は重いんじゃないかな。
語るために選ぶとき、木下順二のを選ぶなら、創作だってことを認識したうえで選びたい。
・・・ここまで
つぎに、昔話の方法を使って作品を書くことが、児童文学を成功させる方法だと、瀬田先生は言います。その具体例。
ヘレン・バンナーバン(1862-1946)
『ちびくろサンボ』1899年(瑞雲舎 刊で読めます)
「お話といえば昔話しか知らない者の口になったように忠実に伝承的な形に従っていて、それゆえに幼年物語の古典たりえた」と言います。

ビアトリクス・ポター(1866-1943)
『ピーターラビットのおはなし』1901年
絵本を中判にしたこと、昔話のスタイルを使ったことで、幼い子をつかんだと言います。
「そのナレーションは、昔話と同様に、まったく経済的でむだがなく、簡素で力強かった。」
ワンダ・ガアグ(1983-1946)
『100まんびきのねこ』1928年 (福音館書店刊で読めます)
マージョリー・フラック(1897-1958)
『おかあさんだいすき』1932年
このふたりは、「昔話のリフレインという明快な展開法と簡潔でビジュアルな表現を存分に示した」
なるほど。昔話のスタイルを使っているから、引き付けられるんだ。

あ、本や絵本の表紙をときどき張り付けてますが、これは、出版社がOKしているものだけです。著作権のことは、クリアしてますよ~
引用文も、それが引用であることをはっきりさせて出典を示せば、OK。